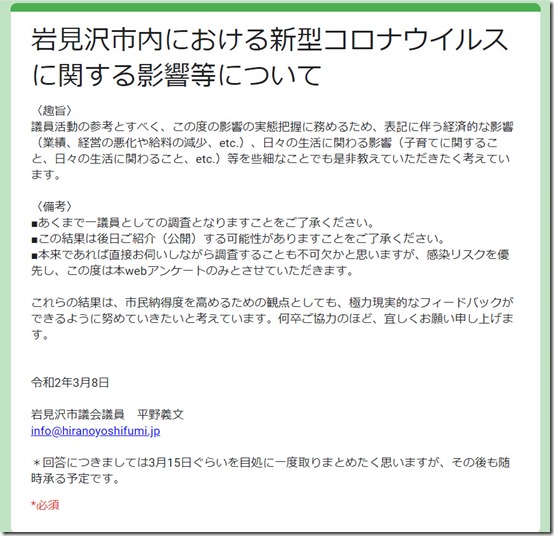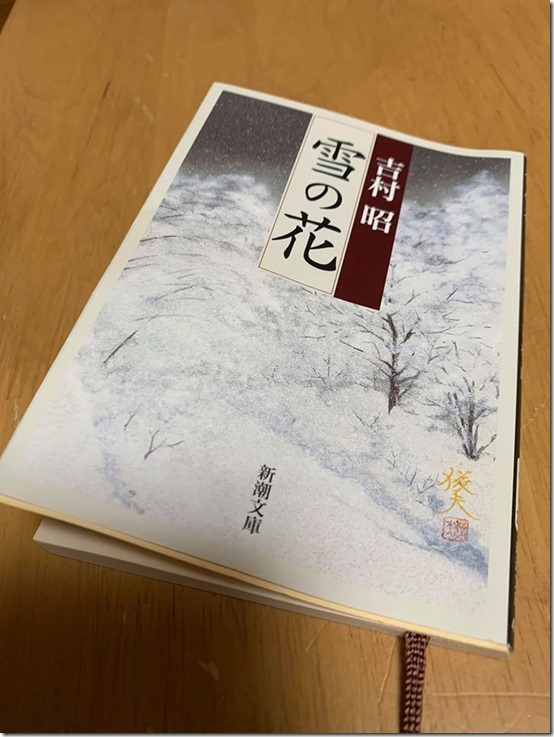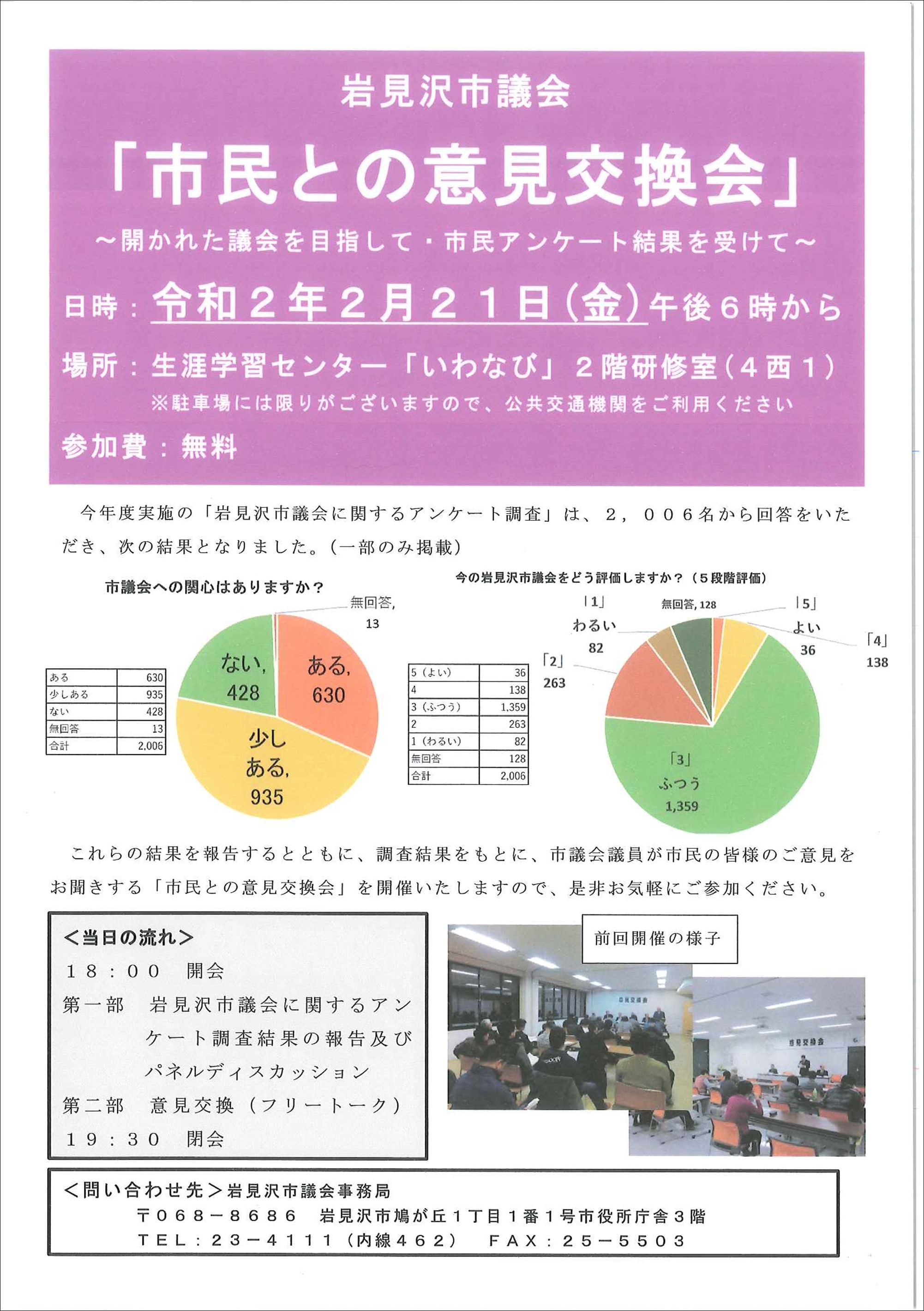〈令和2年3月8日投稿〉
この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事、家庭、日常生活などあらゆる面で影響を受けている方がほとんどだと思われます。
そしてその影響が、我が岩見沢市内においてはどのようなものなのか。それを知ることが議員活動を行っていく中でも重要なことだと考えているところです。
恐らく、飲食業や観光業、サービス業等の方々にとっては、かなり厳しい状況が想像され、子育て世代の方々には休校等による影響も様々に発生していることと思います。そしてそれらの課題は本当に多様で、十人十色であると思われます。
あらためて、市民の皆様がどのような影響を受けていて、それをどう考えているかを率直にお聞かせていただければ幸いです。
とはいえ、せっかくお伺いしたことにも、やはり出来ることと出来ないことがあるのも事実です。しかしながら、あらゆる施策や課題解決に向け、それらの知識、情報を備えているのといないのとでは、雲泥の差が出るものと信じています。
また、できるだけ今回いただいた情報も共有した中で、市民満足度だけではなく、これからの時代にマッチした〈市民納得度〉を高めるための活動につなげていきたいと思っています。
大変お手数をおかけいたしますが、ご協力のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
◇アンケート調査について◇
〈趣旨〉
議員活動の参考とすべく、この度の影響の実態把握に務めるため、表記に伴う経済的な影響(業績、経営の悪化や給料の減少、etc.)、日々の生活に関わる影響(子育てに関すること、日々の生活に関わること、etc.)等を些細なことでも是非教えていただきたく考えています。
〈備考〉
■あくまで一議員としての調査となりますことをご了承ください。
■この結果は後日ご紹介(公開)する可能性がありますことをご了承ください。
■本来であれば直接お伺いしながら調査することも不可欠かと思いますが、感染リスクを優先し、この度は本webアンケートのみとさせていただきます。
これらの結果は、市民納得度を高めるための観点としても、極力現実的なフィードバックができるように努めていきたいと考えています。何卒ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。
令和2年3月8日
岩見沢市議会議員 平野義文
info@hiranoyoshifumi.jp
*回答につきましては3月15日ぐらいを目処に一度取りまとめたく思いますが、その後も随時承る予定です。