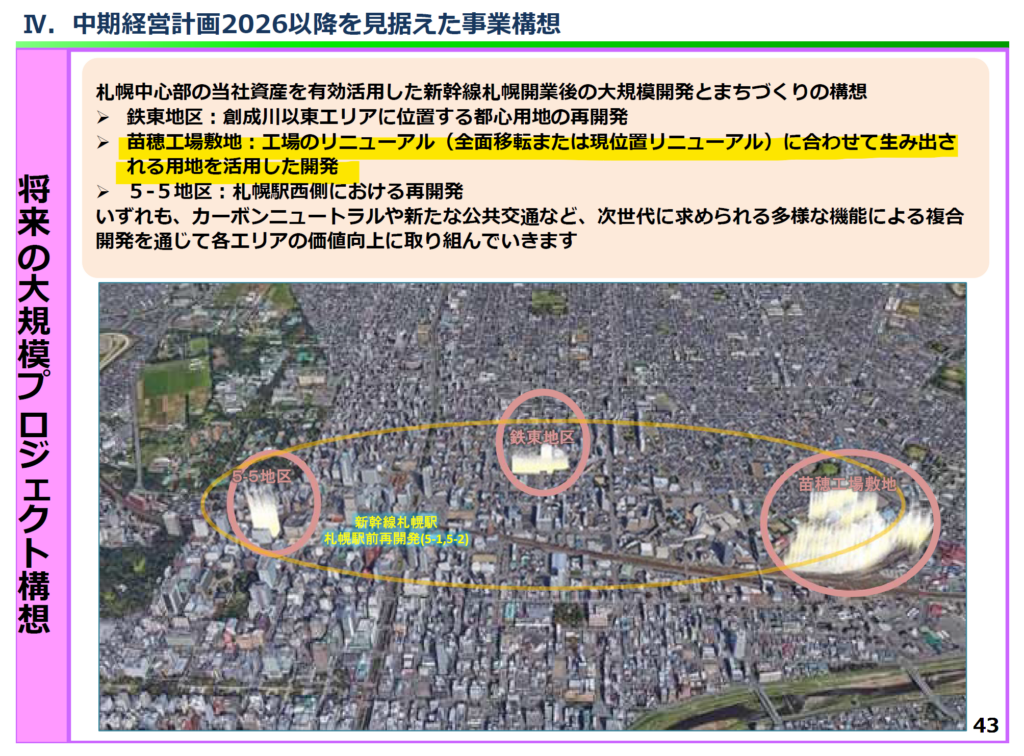平成24年9月の当選以来、本会議にて行った一般質問及び答弁のまとめを掲載いたします。
◆令和5年第四回定例会(12月)《一般質問》
1,再生可能エネルギー普及に伴う現状と今後の対応について
2,新病院建設について
【下記:補足投稿】
VIDEO
◆令和5年第一回定例会(3月)《代表質問》
1,令和5年度予算編成について
2,行政改革大綱について
3,新型コロナウイルス感染症について
4,デジタル技術の活用推進について
5,ゼロカーボンシティに向けた取組について
6,住宅施策について
7,開庁140年、市制施行80周年について
8,教育行政について
VIDEO
*議事録転載
令和5年第1回定例会_代表質問議事録転載
◆令和4年第三回定例会(9月)
1,スマート・デジタル自治体の更なる推進に向けた取り組みについて
2,岩見沢市の有機農業の推進と学校給食への活用について
3,デジタル・シチズンシップ教育について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2023/02/25
VIDEO
*動画映像https://youtube.com/watch?v=jcV58su0O28&feature=shares
◆令和3年第三回定例会(9月)
1、ふるさと納税について
2、市のwebサイトについて
(2)双方向性の活用について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2022/02/10/14776
VIDEO
*動画映像https://youtu.be/NY5dvX6TiEo
◆令和2年第三回定例会(9月) 1,人口減少社会への対応について
(1)項目 現在の人口推移とその対応について
(2)項目 公共施設の状況と今後について
2,ICT環境について
(1)項目 市内ブロードバンド環境について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2021/09/06/13732
VIDEO
*動画映像https://youtu.be/-VSY8v5LKzs
◆令和元年第四回定例会(12月) 1 市が所有・管理するパークゴルフ場の考え方について
(1) 利用者数の推移と動向等について
(2) パークゴルフ人口増への対策と健康寿命延伸への有効活用について
(3) 利用料金の現状について各施設において料金設定の不均衡が生じている経緯について
(4) より多くの人が利用しやすい環境づくりに向けて
(5) 市内パークゴルフ場における一元管理について
2.炭鉄港の取り組みについて
(1) このたびの日本遺産認定を受け、今後の利活用について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2020/10/09/13206
VIDEO
*録画映像https://youtu.be/tMSNQgNiOZk
◆平成30年第三回定例会(9月) 1 炭鉄港推進に伴う地域価値の向上について
(1) 岩見沢の価値に対する認識について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2018/12/16/10631
VIDEO
*録画映像https://youtu.be/LVXzOmR_ZYI
◆平成29年第三回定例会(9月) 1,市役所庁舎建設について
(1)多くの市民と対話できる情報提供のあり方について
*録画映像https://hiranoyoshifumi.jp/2017/09/22/9119
VIDEO
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2017/12/07/9341
◆平成28年第四回定例会(12月) 1、岩見沢市指定文化財について
(1)現状と課題について
(2)今後の考え方について
2,子育て環境の整備について
(1)幼少期の遊び環境について
(2)インターネット、電子媒体等への対応について
*録画映像https://hiranoyoshifumi.jp/2016/12/20/8039
VIDEO
*公式議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2017/02/15/10140
◆平成27年第四定例会(12月) 1 安定した雇用や、活躍する場を増やすための取組について
(1)地元商工業振興について
(2)起業(スタートアップ)支援について
(3)企業誘致について
2 市民活動の機運向上に向けた取り組みについて
(1)活動支援体制の整備について
(2)市民意識向上に向けた仕組みづくりについて
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2016/06/16/7381
◆平成27年第二定例会(6月) 1 地方版総合戦略の策定に伴う考え方等について
(2)公共施設マネジメントについて
(3) 歴史、文化の要素について
(4)広域連携について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2015/08/20/6447
◆平成26年第四定例会(12月) 1 子どもの成長に不可欠な「遊び環境」の推進について
⑵ 現在計画中の屋内型遊び場の運営について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2015/03/03/4781
◆平成26年第二定例会(6月) 1 岩見沢市まちなか活性化計画について
(2)前向きな計画推進にむけた仕組みづくりについて
2 克雪に向けた取り組みについて
3 豊かな人間性を育む教育について
◆平成25年第四定例会(12月) 1 駅前通り整備について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2014/03/27/2848
◆平成25年第三定例会(9月) 1 持続的で活力ある岩見沢市の実現のために
2 公共施設の現状把握と情報共有について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2013/12/06/3215
◆平成25年第二定例会(6月) 1 今後の都市計画について駅前通整備事業について ①進捗状況及び今後の方向性について
2 除排雪事業について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2013/09/09/1834
◆平成24年第四定例会(12月) 1 除排雪について
2 岩見沢市の活力向上について
3 教育環境について
*議事録転載https://hiranoyoshifumi.jp/2013/02/01/6939
随時、追加してまいります。