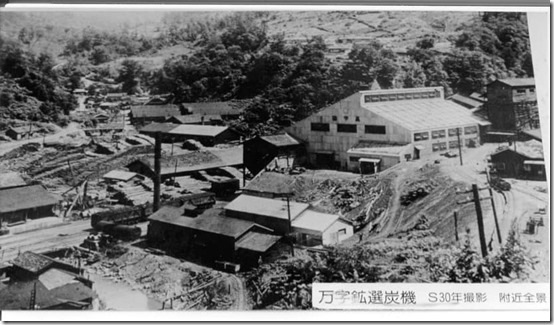〈令和2年11月5日投稿〉
つい先日、貴重なデータを見せていただく機会をいただきました。
授業に関わらせていただいた某小学校のアンケート結果です。
人数が記載されていると大体どこの学校か目星がついてしまうため、パーセンテージだけのご紹介となりますが、授業で岩見沢の歴史や炭鉄港などの背景を知った後に取られた「岩見沢が好きですか?若しくは好きになりましたか?」という設問に対し、98%が「はい」と応えてくれている。
残りの2%は石炭が戦争に使用されたから、、、という理由であったとのこと。その気持も良く理解できます。
授業で関わらせていただいた1学年の内、ほとんどの生徒が明確に「岩見沢が好き」もしくは「岩見沢のことが好きになった」と回答してくれているのは嬉しいこと。「いいえ」と応えた生徒さんも、明確に自分の意見を持てていることにとても感慨深いものがあります。
私自身、細々としかできてはいませんが、岩見沢シビックプライド探求部という活動を通し、この様に岩見沢の子ども達にも地域の価値を伝えることができているのは何よりもありがたいことです。
目指すところは、岩見沢に誇りと愛着を持てるような環境づくり。
まだまだ微力ですが、努力を続けていきたいと思っています。