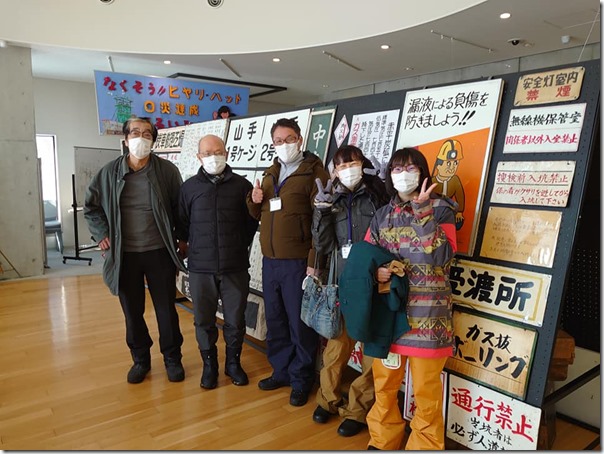〈令和3年8月24日投稿〉
本日の午前中、某小学校4年生の授業に行ってきました。
今回は2クラス同時で行うため、密を避けるためドアを開け放して換気の効いた体育館で開催です。
お話のタイトルは「岩見沢の歴史と炭鉄港」とし、開拓の状況からスタート。その後、岩見沢市が発展した炭鉱と鉄道の話をベースに、日本遺産となった炭鉄港のアウトラインも紹介しました。またそれにプラスして、この学区ならではの歴史的事象についても補足した次第です。

心配だったのは小学4年生にとって、この岩見沢の歴史をお話するには1コマではちょっと厳しい。
しかも北海道開拓の話をするには「明治維新」を避けて通れないし、炭鉱や炭鉄港を語るには「産業革命」が不可欠。これまでの経験上、6年生ぐらいだと比較的面白がってくれるけど4年生にはかなり難解。
それでもこれまでの反省を活かしつつ、より噛み砕いたお話になるように努力したのですが、私もまだまだ修行が足りなかったようで、残念ながら目を輝かせて最後まで聞いてくれていたのは半分ぐらいかな?という印象。他はどうしても頭に入らなくなってしまって、飽きてきてしまう様子が垣間見えた気がします。これは大いに反省事項で、現在の私にとって、この4年生への座学というのが物凄く高いハードルに感じています。さてどうしたものか。。
せめて先にフィールドワークで炭鉱の現場に触れたり、駅周辺を歩いたりできればまた違うかな?と振り返りをしているところですが、いずれにせよ今の学校現場はとても忙しく、先生達も他にやることが満載の中で地域の歴史や炭鉄港のことを調べるのは大変。よって少しでもお手伝いできればと考えていますが、重ね重ね、まずはこの4年生に対する座学が私の大きな課題になっているので、子どもたちのためにも、それを克服できるように頑張らねばなりません!(いかに大人向けに話すのが楽なことか痛感します。)
現在の修正方向としては、どうしても情報過多の傾向があるので、どれかをバッサリ切り捨てるのが必要と思っていますが、考えれば考えるほど、地域の歴史にとってどれも切り捨てることの難しいものばかり・・。いっそのこと2コマならゆっくり更に噛み砕けるのか?それとも1コマのままで情報量を劇的に落とすのかを考えなくてはなりません。まぁ、やはり1コマで情報量を落とすのが正しいのだろうと思うのですが。
なにはともあれ、なかなか学校の先生の様に上手に授業を行うことはできません。
本日も「まだまだ修行がたりないな・・・」と痛感中です。