北海道教育大学岩見沢校の1年生グループと、岩見沢市の人口減少対策チームが連携し、芸術とスポーツの力で地域を活性化するという切り口で「人口減少対策」のアイデアを考えたようです。
その発表会が、平成27年1月29日(木)に16時~17時30分の予定で開催されます。
場所は岩見沢複合駅舎2階の有明交流プラザ センターホールです。
入場無料・事前申し込み必要なしです。
是非お話を聞いてみては如何でしょうか!
私も行きます♪
平成27年1月21日投稿
現在の札幌の大雪による交通麻痺等での多くのfacebook上のコメントや、先日参加した防災訓練の時に再認識したことで、何より大事なことが市民に対する情報の発信なのだと言うことを感じています。
この突発的な大雪の対応に関しても、どうして除排雪が追いつかないのか?という事が理解できれば、市民感情もかなり変化するのではないかと考えているところです。
そこで、二つの出来事をブログにしておきたいと思います。
◇岩見沢でもお正月の記録的な大雪に見舞われたころ。
私のブログが「岩見沢 除雪 苦情」か何かのキーワードでインターネット検索に引っかかったと思われ、ある投稿に下記の様なコメントをいただきました。
平成27年1月13日(火)
第3回目となる岩見沢まちなか未来会議が開催されました。
第一回目は11月10日の開催。
この後、第二回目は12月9日だったのですが、突如解散した衆議院選挙の都合で参加叶わず。1回飛ばしての参加になったため、若干戸惑うところもあったのですが、非常に活気のあるテーブルのお陰で楽しく時間が過ぎました。
このテーブルのテーマは、《子育て世代に優しいまちにするために何が可能か?》というもので、前回までに実際に子育てをしている女性達の発想で、様々に議論がされておりました。
それらを元に、テーブルでもう一歩深いアイデアを抽出。
私も理事をつとめさせていただいています、そらち炭鉱の記憶推進事業団が運営するマネジメントセンターからの情報です。
元URL http://yamasoratan.blog62.fc2.com/blog-entry-1840.html
*******以下転載**************
1月24日(土)、岩見沢で「産炭地活性化フォーラム」が開催されます いつもブログを見て頂いている皆さまに、この場で先行ご案内です!
いつもブログを見て頂いている皆さまに、この場で先行ご案内です!
サブタイトルは、
~産業革命遺産の世界遺産登録に向けた観光・まちづくりを学ぶ~
現在、世界文化遺産登録に向けて推薦されている、
「明治日本の産業革命遺産-九州・山口と関連地域」
本年6月開催のユネスコ世界遺産委員会で登録の可否が審議される事になっています。日本の近代化の飛躍的な発展の大きな原動力となった九州・山口地域。造船、製鉄・製鋼、石炭産業の極めて重要な遺産群が多くあります。大きくエリア分けされている中の、鹿児島を代表する方をお招きして、取り組みや事例を紹介して頂き、北海道産業遺産の活用の可能性を見出します!!
平成26年12月24日投稿
昨日は《SANTA STATION 2014》と銘打ったプロジェクトクリスマス from IWAMIZAWA連携のイルミネーションイベントを開催しました。
点灯時間は僅か2時間にも満たないけれど、儚いのがまた良し。。
そのイルミネーションの様子はこんな感じでした。
平成26年12月20日(土)
岩見沢市立緑陵高等学校 情報コミュニケーション科 第19回課題研究発表会が開催されました。
昨年、基調講演に呼んでいただいた縁で、今年は[1班4名]の学生さん達が「駅まる」との連携を課題に選んでくれ、春から幾度か駅まるの仲間達と一緒に企画を重ね、そして9月に足湯を実施。
それだけではなく、11月には「高校生が考える岩見沢の未来」というシンポジウムを開催していただき、私たちも一緒に楽しませていただきました。
そんな頑張ってきてくれた「駅まる班」の発表もあることから、朝から楽しみに会場へ。。
この課題研究発表会は非常にレベルが高く、高校生であんなに堂々とプレゼンができちゃったら、もっと経験を積んだらどんなになっちゃうの?というぐらいの内容です。
しかしその背景には、学校を飛び出し実際に地域の大人と関わり、様々に試行錯誤しながら経験を積んでいくことから生まれる自信が垣間見えます。その器をつくっている学校と先生達の努力には頭が下がります。
当日は全部で16班の発表があるのですが、そのどれもが素晴らしく堂々としたものです。
自分の息子、娘が、進学に緑陵の情報コミュニケーション科に行きたいと行ったら、是非行かせたい!と心から思うぐらい素晴らしい経験だと思います。
さて、休憩を挟んで、我らが[駅まる班]
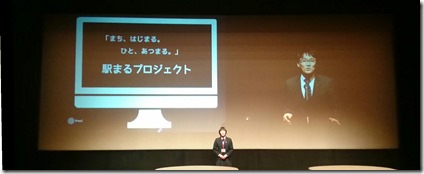
(こんなところにも私を出していただけて、恥ずかしくもとても嬉しかったです。)
贔屓目でみるせいもあるかもしれませんんが、素晴らしいプレゼンを展開。
わずか半年少々ですが一緒に活動してきた学生さん達が、こんなに立派にプレゼンする姿をみて本当に感激しました。
そしてその成果として、、
[発表部門賞]を受賞!
本当に我が事のように嬉しかったです。
最後にほんの少しだけ4人とお話する機会があり、「20歳越えたらみんなで飲もうな!」というのは心から楽しみにしている約束です。
残念ながら卒業後は4人とも岩見沢を離れるとのこと。しかし、きっとまた岩見沢に戻ってきてくれる事でしょう。
そんな事を楽しみに、彼ら彼女達が帰って来られる、帰って来たくなるようなまちをつくっていかなくてはなりません。
いずれにせよ、このような素晴らしい経験を生徒にさせることができている緑陵高校情報コミュニケーション科の活動には心から敬意を表します。(それだけにスポーツの方は何とかもう一踏ん張りしていただきたい。)そして、このような活動も予算ゼロに関わらずに受け入れてくれている各種事業所、団体、個人等がいて成り立っていることも多くの人に知って欲しいことの一つです。そんな温かい環境をみると世の中まだまだ捨てたもんではありません。
また来年、多くの生徒さん達が地域の大人と交わり、そして成長していく姿を見てみたいと思います。
ちなみに。。
今年の基調講演は㈱ZAWA.comの佐藤直輝社長。
自身の経験からほとばしる深いお話をしておりました。
彼も岩見沢の将来になくてはならない人財の一人です。
来年の課題研究発表も楽しみですね!
平成26年12月23日(火)
もうすぐですが・・・
ゲリラ的に岩見沢駅前が輝きます!
というのも、せっかくプロジェクトクリスマス from IWAMIZAWAの皆さんが頑張っておられることもあり、駅を中心にまちづくり活動をしている「岩見沢観光振興ビジョン駅まる部会」としても何かできないか?という展開です。
今のところ、あまりに突発ゆえ、イルミネーションをメタセコイアの周囲に敷き詰めるという作戦でいく予定ですが、現在どれぐらいの電球を手に入れられるかの最終チェックをしてから飾り方が決まります。
唐突にゲリラ的実施でありまして、12月23日は朝から現場でセッティングをはじめます。
そして16時に点灯し、18時には撤収開始の予定!!
初めての今回は、わずか2時間ばかりの儚い贅沢イルミネーションです。
当然、それだけでは寂しいので、添付のポスターの様にセンターホールでもミニライブや子ども達へのクリスマスプレゼント(先着50名)もあります!!緑陵生の開発した商品もイワホで買える特別な日です。
12月23日(火・祝)は、16時から岩見沢駅にいらしてください。
今年一番のシャッターチャンスの時間は2時間のみですヨ!!
お子様連れだけでなく、カメラ連れの皆様のお越しをお待ちいたしております。。
平成26年11月22日(土)14時~16時
岩見沢複合駅舎センターホールにて表題の様なシンポジウムが開催されました。
主催は緑陵高校生!
実はこの日、私は衆議院解散に伴う会議が2件入り、会場と駅を行ったり来たりの慌ただしい一日となりましたが、とても楽しい時間を過ごさせていただくことができました。
このシンポジウムは緑陵高校情報コミュニケーション科の「駅まる班」が企画してくれたもの。
遡ると、昨年の12月に課題研究発表会の基調講演をさせていただき、その時に「駅まる」の活動に関心を持ってくれた4名の生徒さんが、4月の新年度のスタートと同時に、課題研究のテーマとして「駅まる」に関わりたいと言ってきてくれたもの。
それが縁で、9月の駅まるイベントの時には「足湯」を実現してくれました。
そんな駅まる班の集大成としての一日になりました。
最初は僭越ながら、私の基調講演から始まります。
ここでは、これまでの「岩見沢駅」を中心としたまちづくりがどういう経緯で発生してきたか、またこれからどんな事をしていこうと考えているかをお話させていただきました。
ただ、非常にボリュームのある内容をわずか30分の持ち時間で流してしまったので、ちょっと飛び飛びの不完全燃焼気味でしたが、一応、緑陵生は昨年の12月にお話したことと重複する部分はサラッとで。。
この次が緑稜情コミュの3班による活動報告プレゼン。
三笠高校や企業と組んで商品開発をした班と、岩見沢のゆるキャラの「いわみちゃん」を活用して岩見沢の情報発信に努める班、そして駅まる班の3つでした。
どの活動も素晴らしく、自分が高校生の時と比較すると雲泥の差があります。
最後に班毎に講評の時間があるのですが、それを駅まるの和田専務と私で担当。。どの発表も素晴らしく是非とも12月の報告会本番では評価を得られるようになって欲しいと願うばかり(報告本番は12月20日 (土)入場無料、どなたでもご覧になれます。詳細はまた後日。)。
この報告を聞いた大人は誰しも「今どきの高校生は凄い!」と言わさると思います。高校生でありながら、大人の中にどんどんと入っていき、自分たちの課題を実現するために意思を表現して、そして力を合わせて現実のものとしていく。
この緑陵高校の情報コミュニケーション科の課題研究というものは、「活きた教育」という面において本当に素晴らしいものだと感じます。
最後はこの3班の代表と緑陵の川崎先生、そして私の5名によるパネルディスカッション。
進行も駅まるスタッフと高校生が連携をして、非常に上手に仕切ったり時に笑いの渦になったりと和気藹々のディスカッション。
それぞれのパネラーはぶっつけ本番。私たち大人は慣れていますが、高校生は人前でも緊張することなく、都度与えられたお題に対して自分の意見を明確に述べていき、会場内を頷かせていました。
こういう生徒を育てることができる先生の能力というのも見事なものだと感じさせられますし、実際にパネラーとして登壇していた川崎先生の言葉においても、これまでの数年間で培ってきた成果や苦労を聞くことができました。
また、高校生の発言においても、苦労して自分たちで経験してきたからこその言葉が出てきて観衆も頷くばかり。
こういう生徒達が、まちづくりとか地域活性化という言葉を多用し、これまでの実経験から、上辺のイベントなどではなく人と人との繋がりが大事だなどという意見があったり何とも頼もしい限り。
今どきの若い人は・・という言葉は良く聞くものではありますが、全くそんなことはなくとても頼もしいです。
是非、こんな若者を応援できる私達でいれたらと思うとともに、言葉ではなく背中で教えていけるような人間でありたいとも願っています。
まずは取り急ぎ、、素晴らしい1日でした!というご報告を。
平成26年11月10日(月)
北海道教育大学岩見沢校「地域プロジェクトⅠ」という授業の中で講義をさせていただく機会をいただきました。
これは昨年の11月にも同じ様な機会がありましたが、この時は選択科目で、ごく少数の生徒さんの前で講義をしました。しかし今回はスポーツから音楽、美術、ビジネスまでの全1年生約180人を対象とした授業でした。
私の前に
①岩見沢における文化イベントについて
②岩見沢の歴史について
③岩見沢の社会包摂について
④岩見沢、空知の炭鉱について
という授業があって、当初私に与えられたテーマは「鉄道」でありましたが、私は残念ながら生粋の「鉄道ファン」ではないため、そのネタで90分は無理すぎます。そこで、「岩見沢の生い立ちと鉄道からみるまちづくり」と題して準備をさせていただきました。
時間が迫り、ぞくぞくと集まってくる大勢の大学1年生のオーラに圧倒されつつ、アウェー感満載でスタートするものの、真剣な顔をして随分と熱心に聞いてくれる学生さんがチラホラ見受けられ、おのずとこちらもリラックスして行うことができました。
もちろん、私も学生当時はそうであったように、始まると同時に「今日は寝る!」と決めてくるような時もあるので、スポーツ専攻の一角では始まった瞬間に前傾姿勢に入る学生がチラホラ・・。しかも時間は午後1時の午睡を楽しむ良い時刻・・。