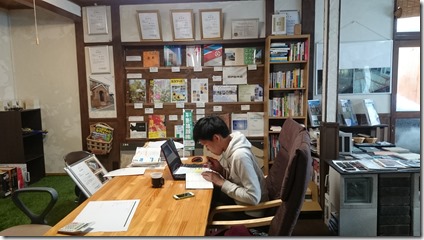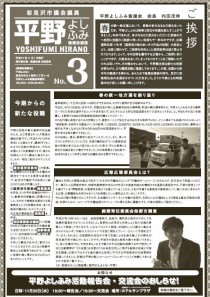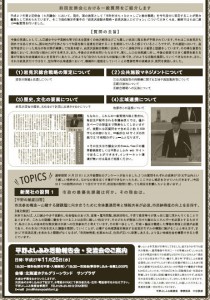2月から3月一杯まで、NPO法人ドットジェイピーより、1名インターン生が来てくれています。ここではK騎君と呼ばせていただいますが、某大学の2年生です。
議会活動のみならず、色々と地域活動にも触れてもらえたらと目論んでおり、何とか非日常を味わってもらえるようにできたら良いなと思っています。(上の画像は第一回目のシビックプライド探求部勉強会の公開用レポート作成中の図)
一番最初の慣らし運転の日。
NPOドットジェイピー運営スタッフのSちゃんと一緒に来岩。
少ないながらも各所で名刺交換等を。。
2月17日は岩見沢CIVICPRIDE探求部の運営手伝いをしていただく。
終了後の懇親会でも周囲と上手く溶け込み、帰りのJRでもそこで出会った方と一緒に大人の乗り方(?)を教えてもらった模様。
JRで一緒に帰った参加者の方に後日お会いしたところ、大変面白い人物だ!と褒めておりました♪
2月20日の午前中は、北海道教育大岩見沢校のあそびプロジェクトで実施した「プレーパーク」のお手伝い!
地元の大学生と共に、子ども達とわいわい活躍しておりました。
そしてこの日の午後は、岩見沢市議会フォーラム 元気UP岩見沢を見学。
午前中の楽しげな雰囲気から一転し、厳しい意見交換等のやりとりに驚いた模様。
26日(土)はIWAMIZAWAドカ雪まつりで開催した鉄道オモチャコーナーのお手伝い!
この日は.JPスタッフのAちゃん(着座左)も一緒にお手伝い。
外は寒いせいもあるのか、親子連れが続々と遊びに立ち寄っていきます。
K騎君はそこで車両の電池交換に追われ大忙し(笑)
沢山の子ども達と触れあっておりました。。
こちらはドカ雪まつり名物のキジ鍋!
YEGさんの粋な計らいで1000食分の釜に携わるチャンスをいただきました。なかなかこういう経験はできませんね♪
そして3月1日からは第1回定例会開会。
会派の皆様にも快く迎えていただき、すっかり溶け込みつつあります。コーヒーを淹れるのも少し上手くなりそうです(笑)
できるだけ各種会議や本会議等の傍聴を経験し、議会がどのように運営されているのかを感じてもらえると良いなと思っています。
3月一杯は行事があれば私の傍らにK騎君がおります。なかなか積極性のある若者です。是非かわいがってやってください。