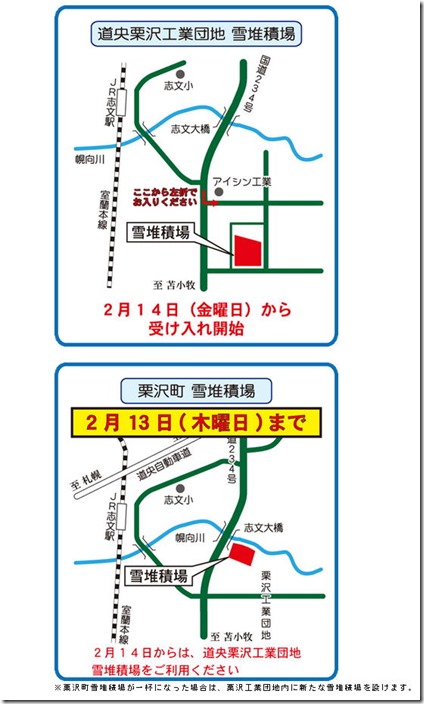平成25年3月21日(金)
岩見沢の地において自由民主党第十選挙区支部青年局研修会が開催されました。
通常は講師の方をお招きしての講演会となるのですが、今回は若者世代の政治離れや世の中の政治に対する期待感の喪失等々を鑑み、あらためて「政治とは何か?」という視点で開催する事となりました。
その演題は、、
「世を変えるには政治の力が必要不可欠!」
~あらためて政治とは何か!私たちが出来ることは何かを考えよう~
というテーマでトークセッションを開催。
ステージゲストとして、
衆議院議員 渡辺孝一様 / 北海道議会議員 村木中様 / 10区青年局長であり夕張市議会議長である高橋一太氏の3名を軸に、力不足ながら私が進行役を務めさせていただきました。
あらためて、国政、道政、市政という3つの階層の中で、政治がどのような流れになっているのか。そしてその持つ役割について80分間のあっという間のトークセッションとなりました。
私自身、政党色が強いわけでもなく、また依存しているわけでもありませんが、縁あって10年ほど前から自民党の党籍を持ち、様々な機会で勉強させていただいています。
現在のような風潮の中で、特に市町村レベルの議員であれば、こういう党籍を持っている事を公言するというのはむしろ逆風の要素が強いのかもしれませんが、私自身、今の政治情勢を考えると色々と懸念すべき点もありつつ、しかし、様々に政治について触れ、国政から市町村レベルの政治まで、縦横の連携を含め、あらゆる勉強になる環境を得られていることに感謝をしている次第です。
そんな想いから、今回のトークセッションも一人でも多くの若者世代に、政治の大切さをお伝えできればと考えたものです。
上手く伝わったかどうかはわかりませんが、私自身は、また大きな勉強をさせていただいたと感じています。