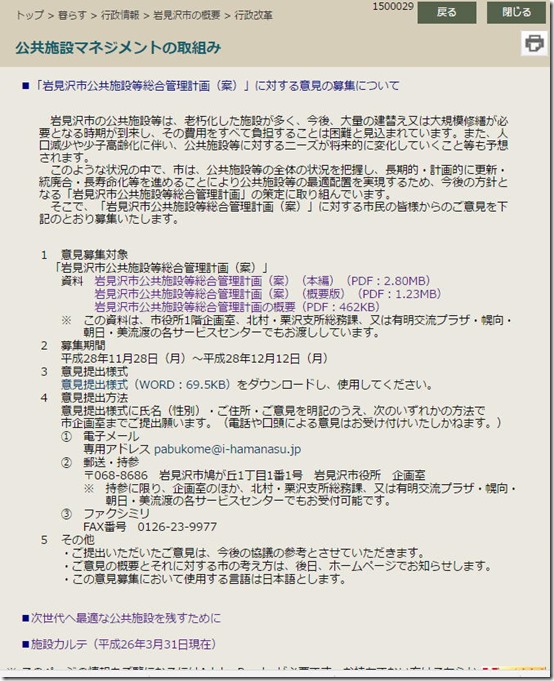〈平成29年1月10日投稿〉
岩見沢市民の方々も重々ご承知のことと思いますが、今日から44日後の2月23日~26日まで、日本商工会議所青年部の全国大会が岩見沢で開催されます。
これまで36回の開催を重ねてきて、岩見沢の様な小規模の自治体で開催されるのは初のことと聞いています。それほど大きな重責を担う大会です。
どれぐらいのスケールかというと、こちらの公式ホームページを見てもらえると雰囲気がつかめると思いますが、大会期間中、岩見沢に4,000人以上の人が訪れるというものです。
非常に努力している岩見沢商工会議所青年部の皆様の動きを見て、また、岩見沢を訪れてくれる全国の方々を迎えることに対し、一市民として何をもって応援できるか?議員としても何かできること、やるべき事は無いのかな?という事を考えています。
まずは1月19日(木)18時より〈市民説明会〉があると聞いています。是非私もそこに顔を出してみたいと思っています。
また、この大会を成功させるためには、やはり市民の後押し&応援が重要なのだろうと感じています。何かできたら・・。と思っていてもどうしたら良いかわからない等のこともあろうかと思いますので、その様な方は、是非上記市民説明会に参加してみては如何でしょうか。
【市民説明会は以下の通りです。(正確な情報が見つからないので記憶を頼りに)】
◇日時:平成29年1月19日(木)午後6時より
◇場所:岩見沢商工会議所2F
恐らく事前申し込みは必要ないのだろうと思います。
またとない折角のチャンスなので、是非、来岩してくれた方々に岩見沢を素敵なまちだと思ってもらえるような大会になれる様、市民みんなで歓迎の雰囲気をつくり上げられることを期待しています。