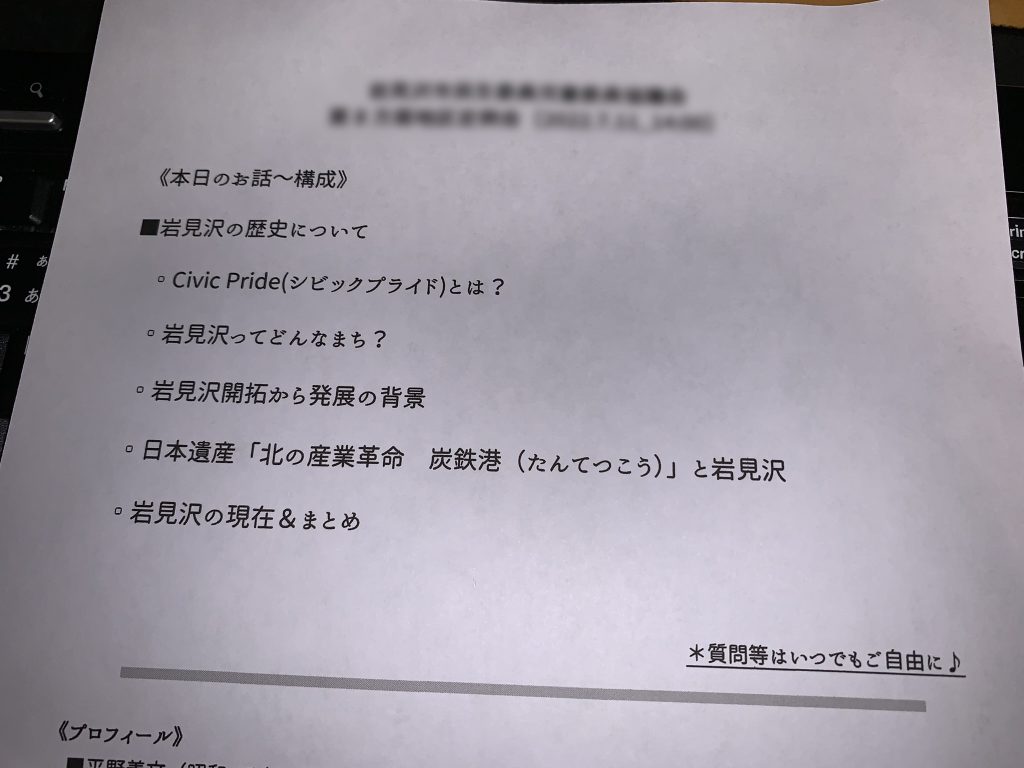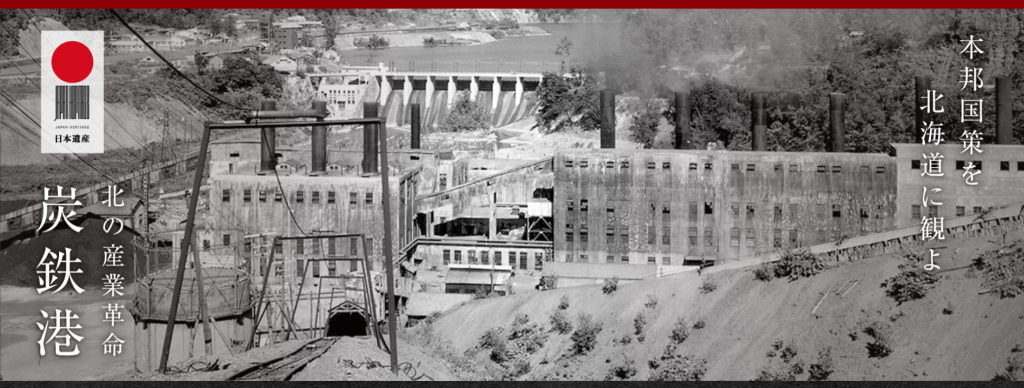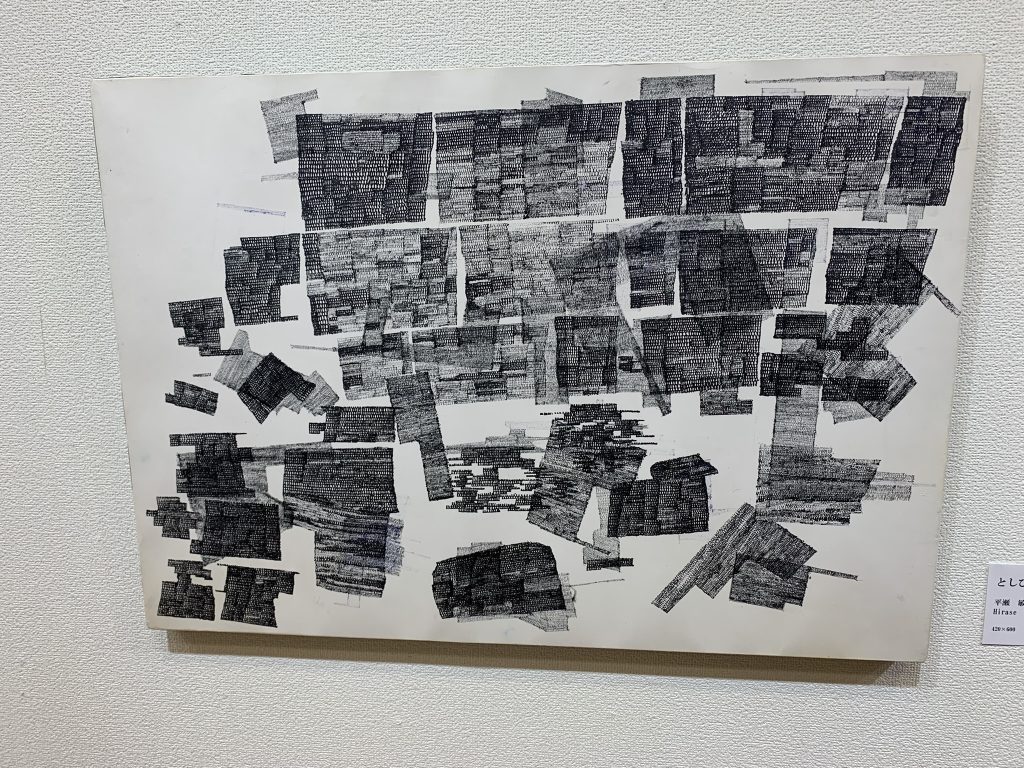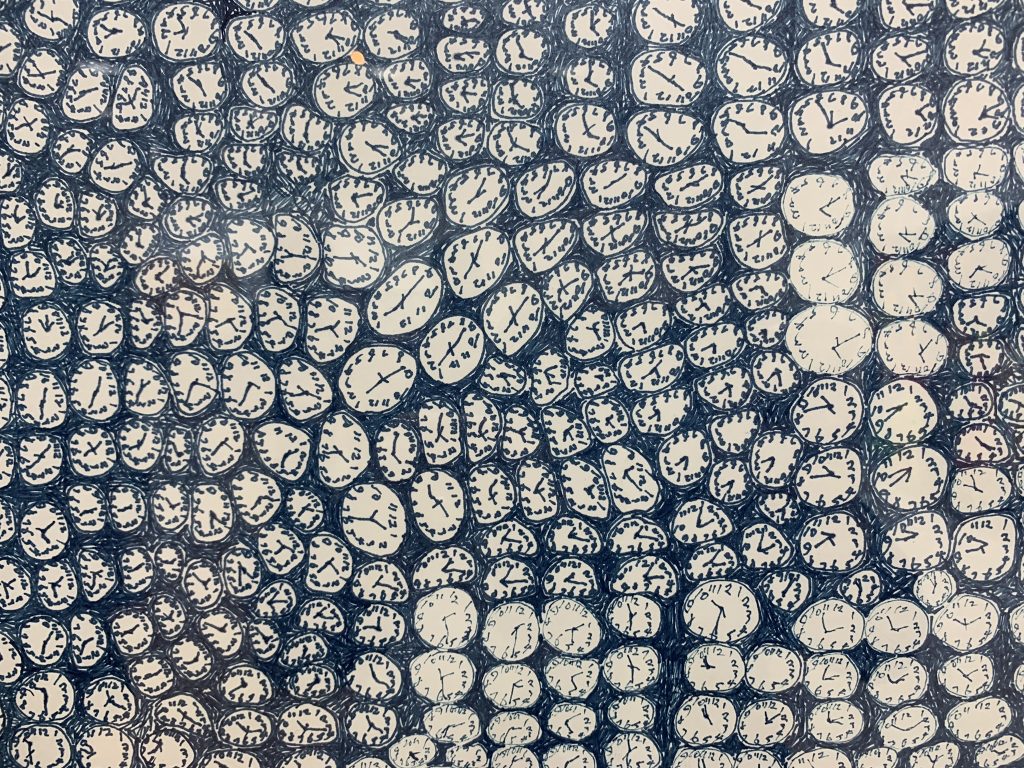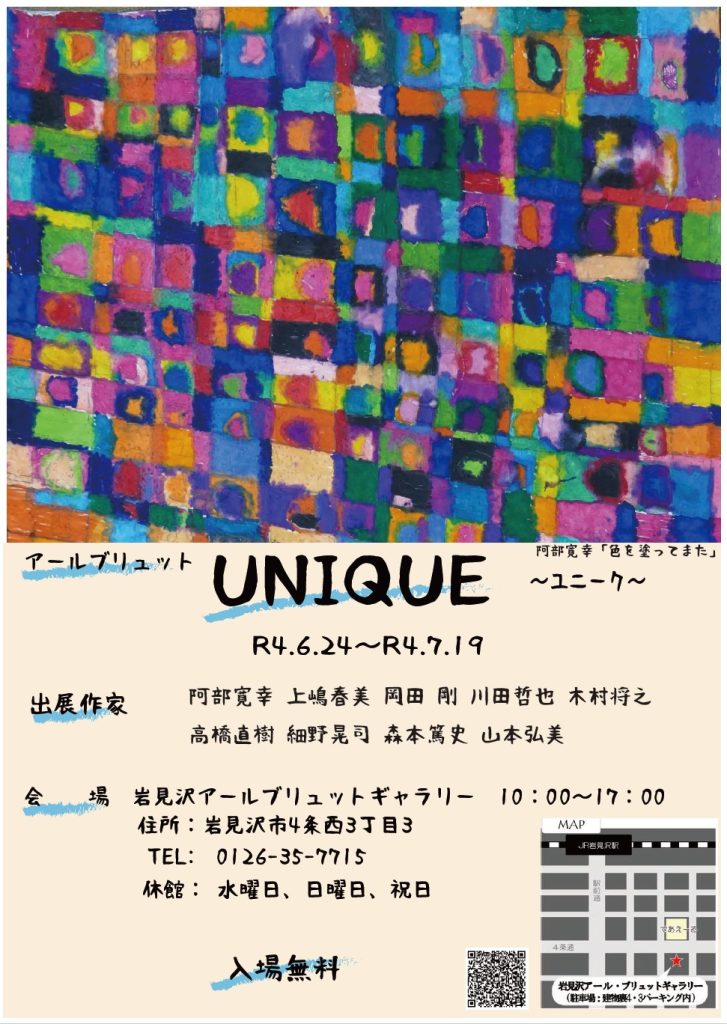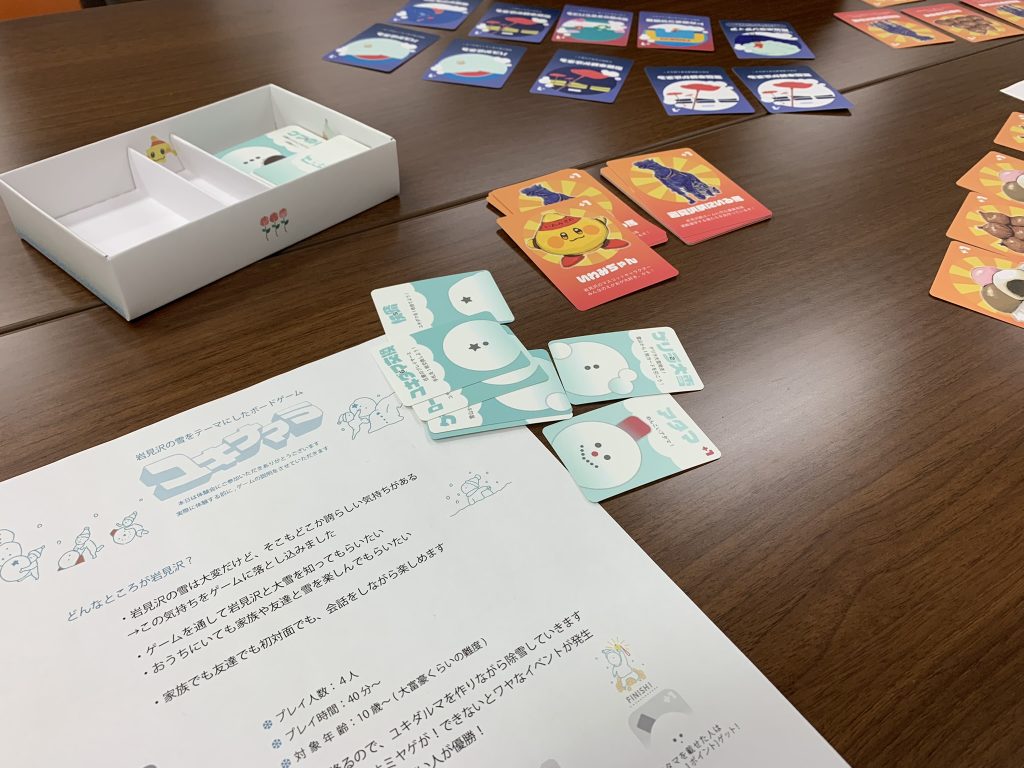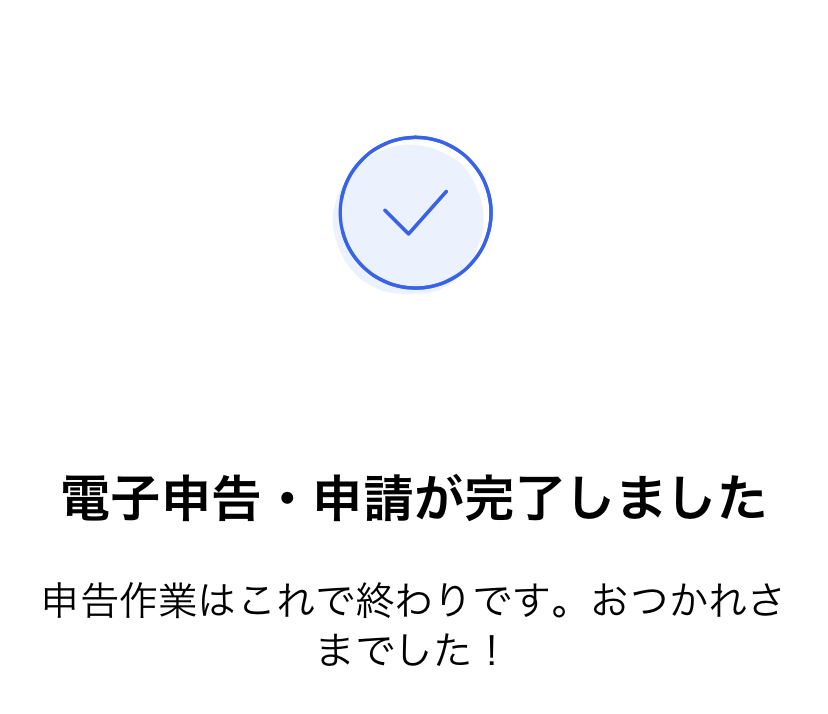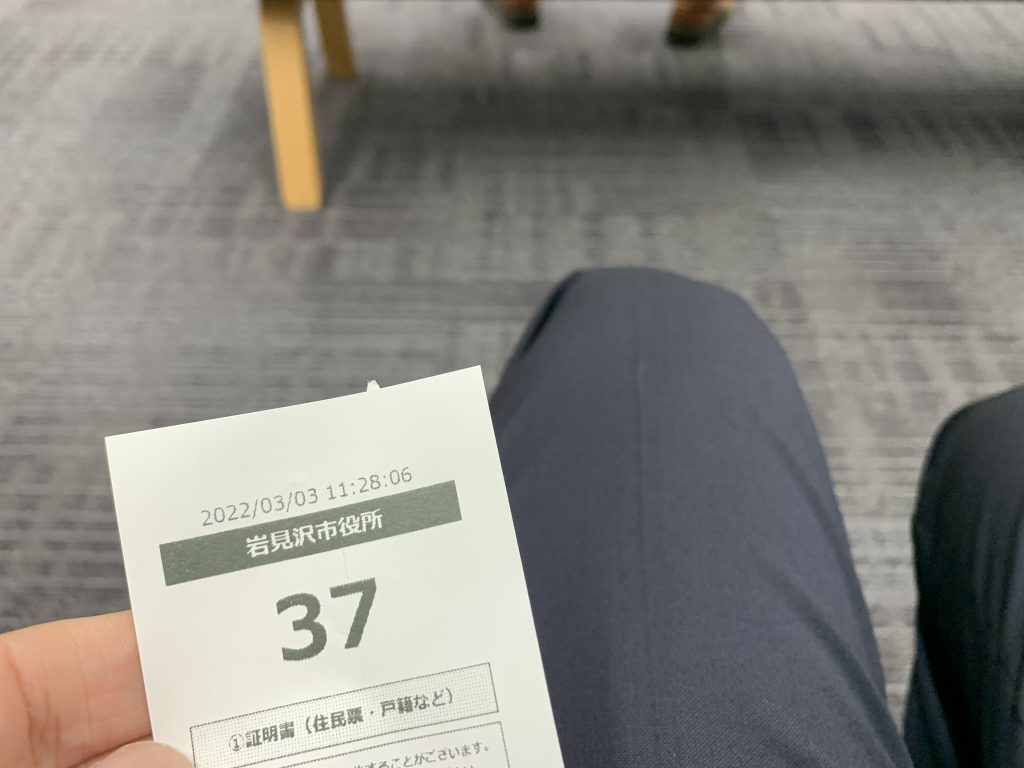〈令和4年7月18日投稿〉
7月17日(日)生憎の雨の中ではありましたが、岩見沢市北村にある空知鉄道さんの延伸開業記念式典が開催されました。

(式典には新聞社やテレビ局の取材も入る本格的なものとなりました)

実は私自身、9年前にこの地に庭園鉄道が誕生した時から、間接的ではありますがご縁をいただき、その後ことあるごとに間近にその進化を見させていただいた経緯があります。
空知鉄道は民間の敷地に個人で敷設された庭園鉄道です。
代表は金森さん。
最初は宅地1区画で約45mの線路敷設による運営だったのが、3年前に隣接した土地を入手。そこから3年後の7月17日(日)に開業式典を行うと決め、コツコツ・コツコツと作業を進め、この度約90mの延長となり、駅が3つ、車両基地が1つの規模へと成長し、予定通りにこの式典が開催されました。
あらためてその実直さに敬意を表したいと思います。

本式典では、私もご挨拶させていただくき機会をいただき、その実直さと地域を愛する心。そしてこの地を訪れる猫ちゃんとのエピソードがtwitterでバズり、ヤフニュースのトップページに載る強運。さらにこの開業を目前に空知鉄道そのものが存続の危機に合いながらも、持ち前の誠実さで課題をクリアしてきた突破力。
これら「実直さ」「強運」「突破力」「地域を愛する心」があれば、今後の発展も間違いなし。北村のみならず、岩見沢、空知と波及していき、多くの人の笑顔が訪れる場になることを期待している旨をお話させていただきました。
この空知鉄道さんの一般開放は、7月18日、8月21日、9月18日、10月16日となります。
ちなみに式典の翌日は18日は一般開放日で、北海道新聞さんの朝刊にも掲載されたことから、過去最高の来場者に恵まれた模様です。
詳細は下記リンクをご覧ください。