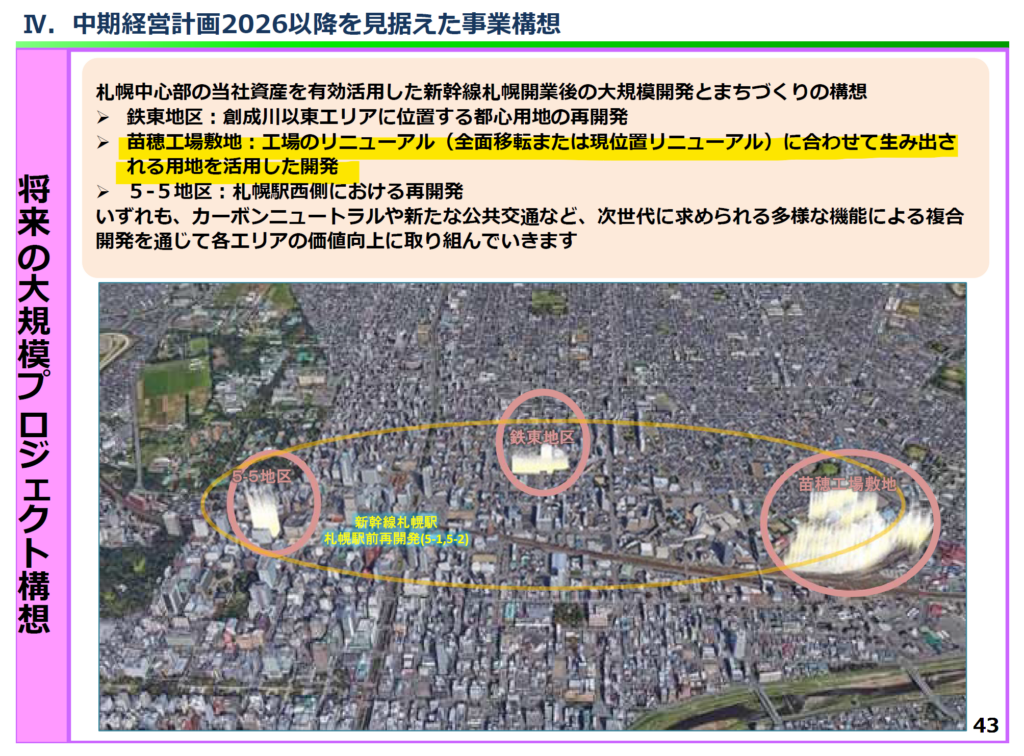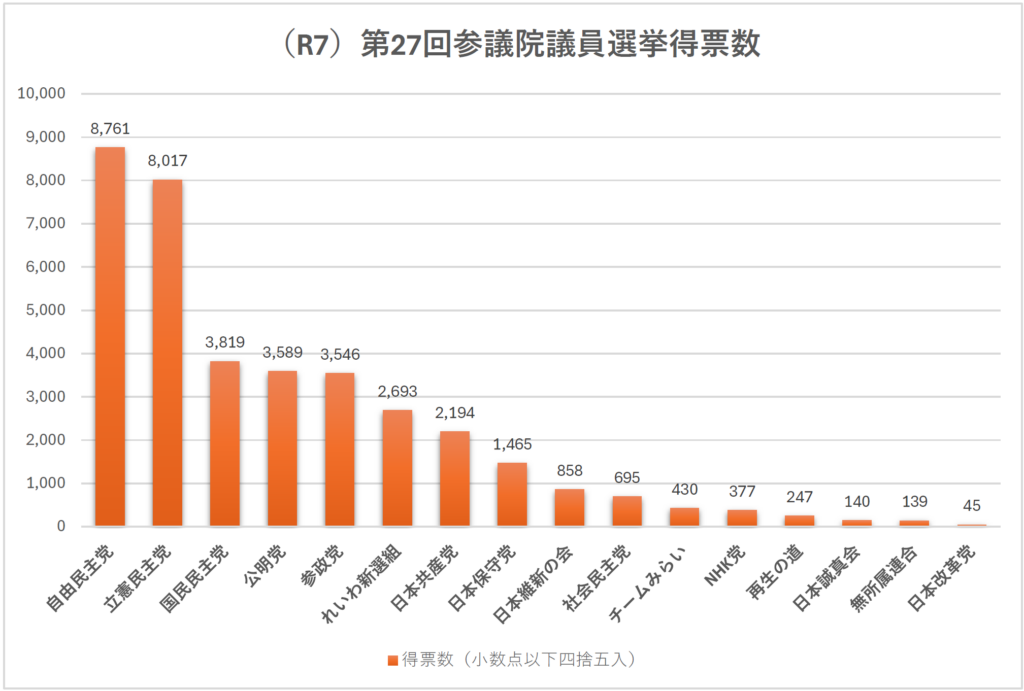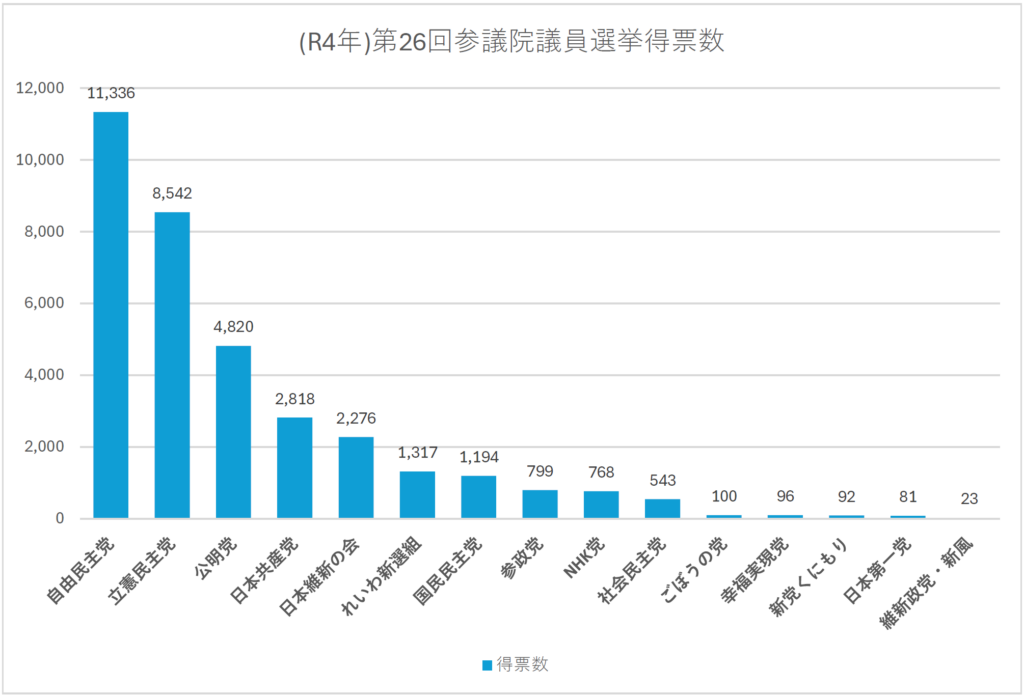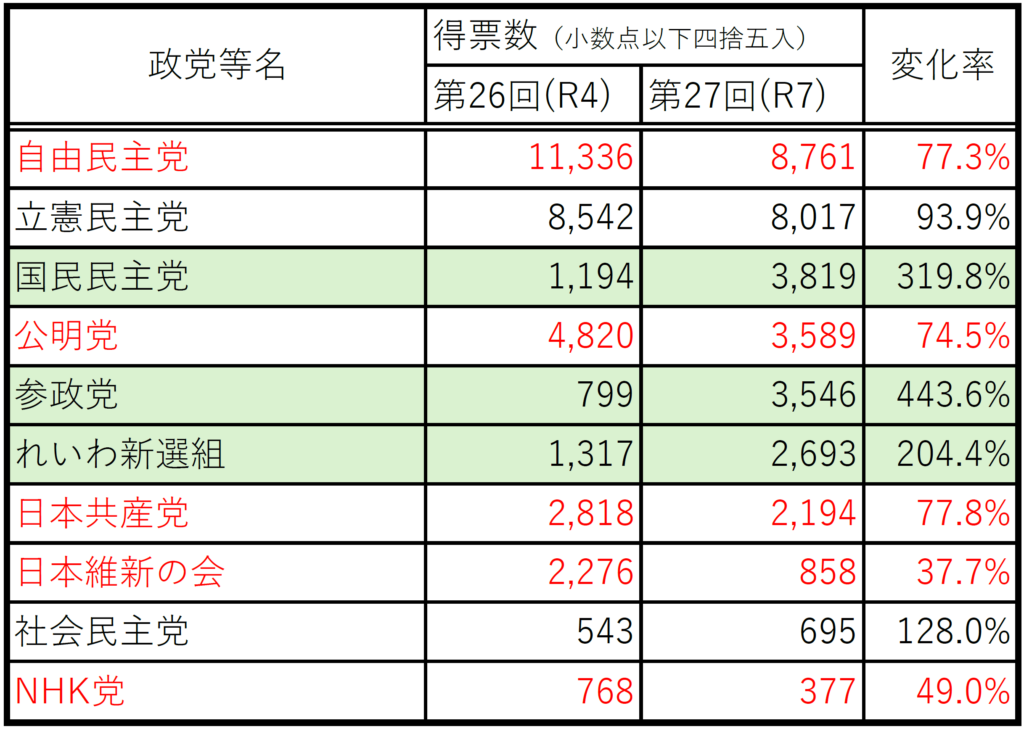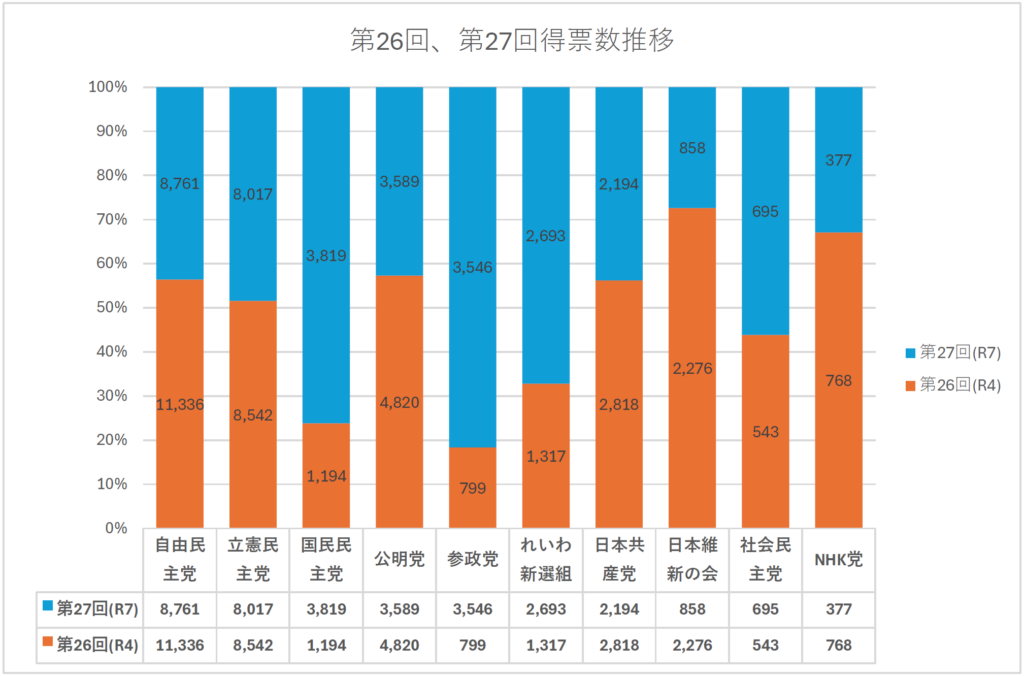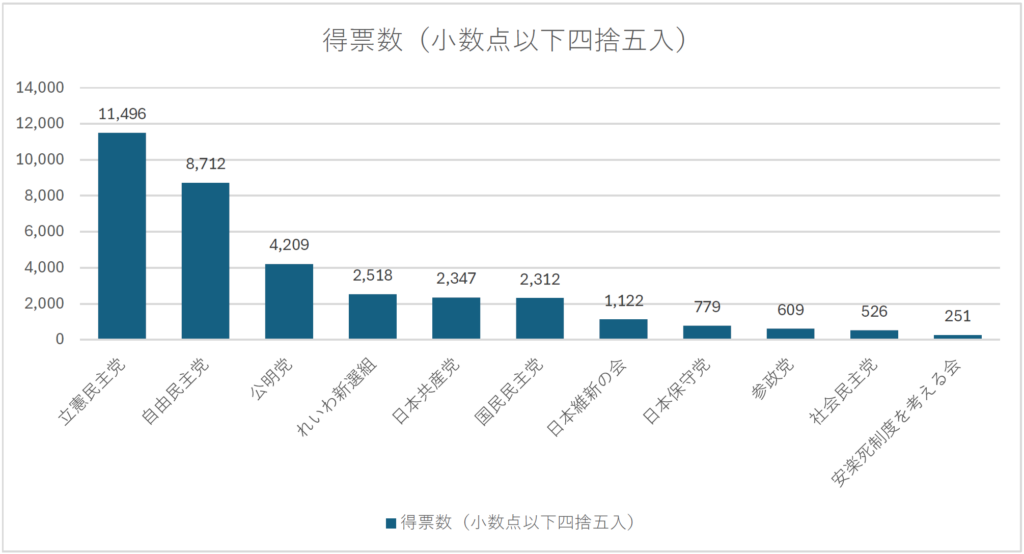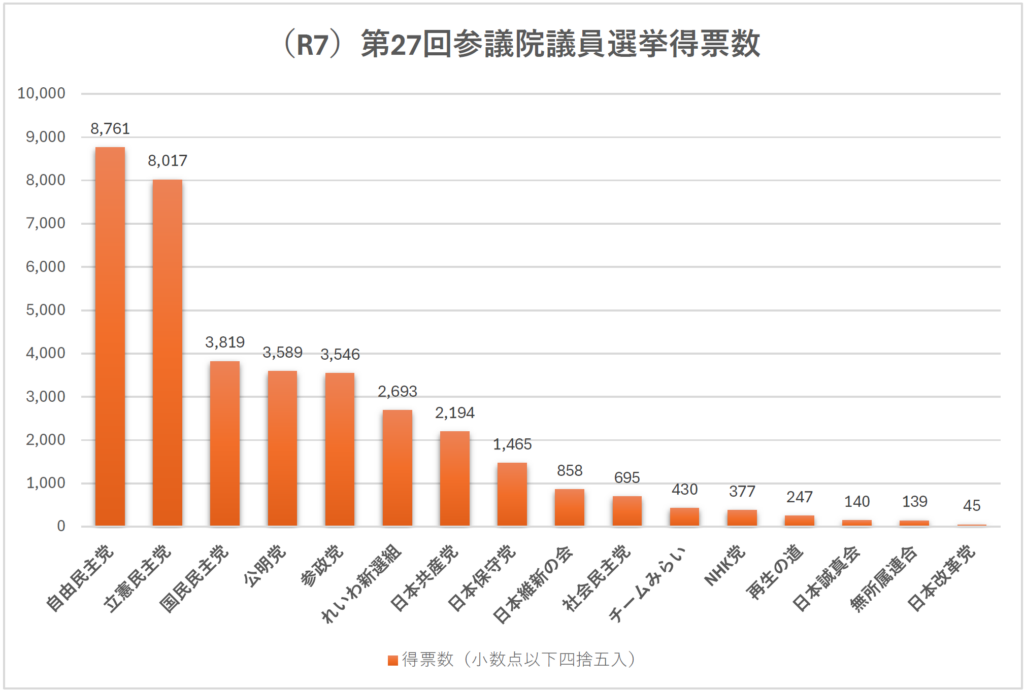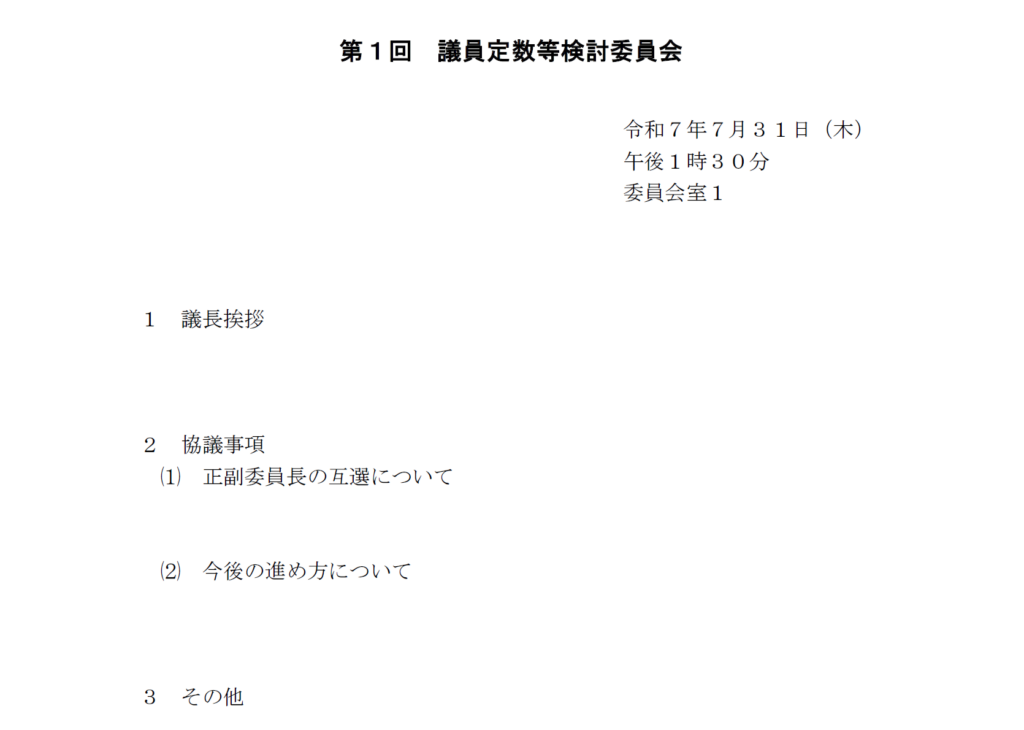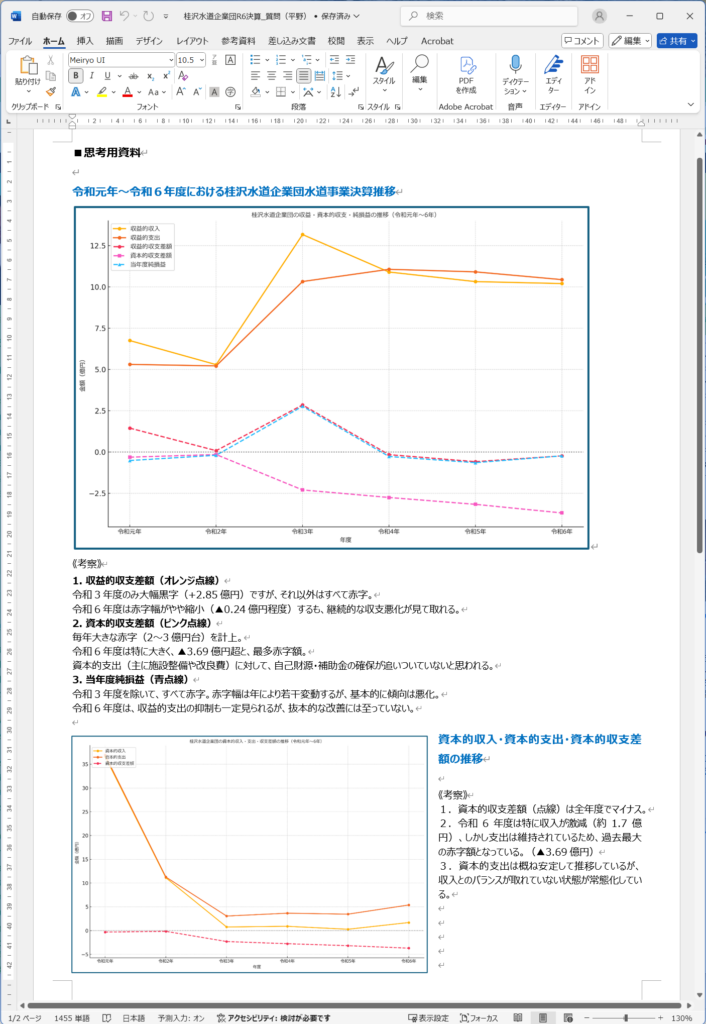〈令和7年8月17日投稿〉
令和7年第2回定例会において実施した一般質問のYouTube動画を、生成AIであるGoogleの【NotebookLM】に読み込ませ、質問と答弁を要約したものを転載いたします。
5.小中学校の統廃合・再編に向けた考え方について
(1)現状と将来予想を踏まえ、小中学校の統廃合・再編に向けた検討について
【平野質問】
・少子化と人口減少により小中学校の教育現場に構造的課題が生じていることを指摘。
・中学校では生徒数減少による部活動の選択肢の限界や指導者不足、小学校では学級数減少による編成・配置の困難さを挙げ、小中学校の統廃合・再編を本格的に議論する時期に来ていると提案した。
・統廃合のメリットとして、児童生徒間の交流促進、教育内容の充実、教職員配置の最適化、施設維持費削減によるICT投資、教育格差是正を挙げ、デメリットとして通学距離・安全性の問題、地域コミュニティの希薄化、子どもの心理的負担、保護者や地域の不安・反対への対応を挙げた。
・子どもの利益を最優先し、住民や保護者との丁寧な対話と合意形成が不可欠と強調。
・学校統合は教育だけでなく地域振興や公共施設再配置に関わるため、市長部局との連携や、統合後の地域振興、代替拠点(会館、子育て支援施設など)の整備も総合的に議論すべきと提言した。
・教育長に対し、少子化が進行する中で学校運営の持続可能性が問われている今、地域との対話も含め本格的に議論を始めるべきではないかと質問。
・教育委員会としての現時点での課題認識、統廃合再編の方向性、そして地域との対話をいつ頃から始めるべきかといった時期的な見通しについて見解を求めた。
【教育長答弁】
①現時点での課題認識と、統合・再編の方向性をどう捉えているか
・岩見沢市は令和2年7月に「小中学校適正配置計画」を策定し、令和5年度までを前期、令和6年度から令和10年度までを後期としている。
・後期計画策定では、現段階で児童生徒数や学級数に大幅な減少がなく、隣接学校の教室に余裕がないため、現状の学校配置を維持することとした。
・ しかし、市内全体の児童生徒数は過去5年間で1割以上減少し、今後10年でさらに4割近い減少が見込まれる。
・年間出生数も過去最小となり、少子化は急速に進行しており、児童生徒数の減少は避けられないと認識している。
・適正規模(小学校12学級以上、中学校6学級以上)の達成が、今後ほぼ全ての学校で困難になると見ている。
・また、築20年以上の校舎が約半数を占め、老朽化による修繕費増加や燃料費高騰により、施設維持費が教育委員会予算を圧迫している。
・これらの状況から、学校の統廃合再編の必要性は一層高まっていると考え、これまで以上にスピード感を持って今後の方向性に関する検討を進めていく必要があると認識している。
②地域との対話等を含めた時期的な見通しについて
・岩見沢市では中学校区を基盤としたコミュニティエリア構想を推進しており、学校は地域コミュニティの重要な拠点施設と位置づけられている。
・統廃合再編の検討にあたっては、保護者や学校関係者、地域の皆様などとの対話を重ね、丁寧に進めていく必要がある。
・現在の適正配置計画が令和10年度までであるため、次期計画の策定も視野に入れ、令和10年度以降に、対象となる地域の皆様との意見交換も含めた議論を始めることができるよう、通学区域審議会の設置や意見聴取を見据え、市長部局とも連携を図りながら統廃合再編の方向性について検討を進めていく。
公式な議事録は現時点でまだ未公開のため、YouTube配信のURLを生成AIの「NotebookLM」に読み込ませて要約したものとなります。多少ニュアンスの異なる点などがあるかもしれませんことをご了承ください。