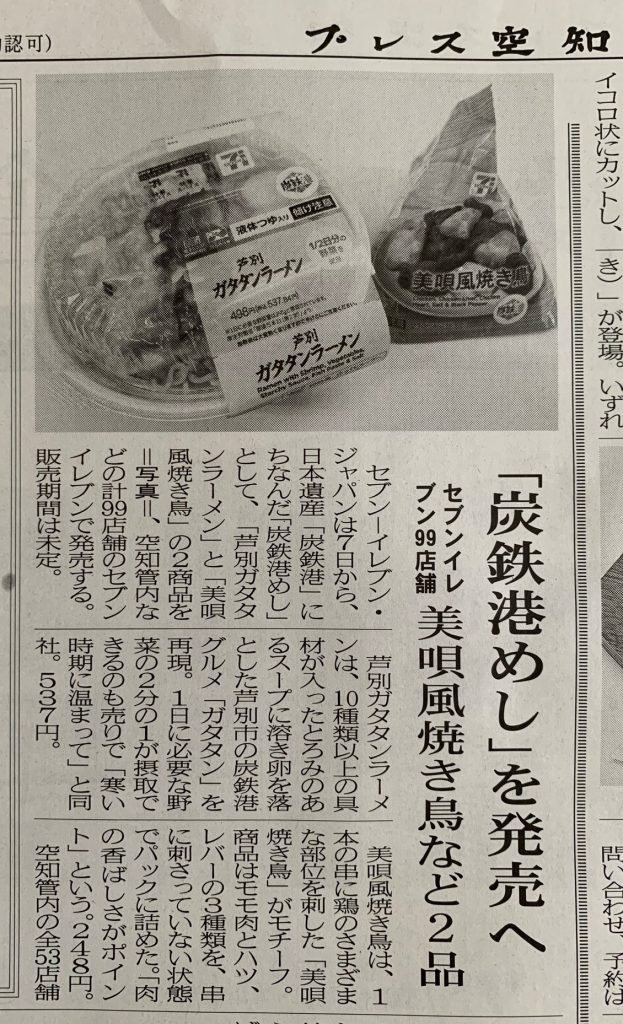〈令和4年2月3日投稿〉
1月27日、(仮称)万字ズリ山愛好会の皆さんに同行させていただき、初めてのスノーシューハイクをしてきました。おかげさまで天候にも恵まれ、爽やかなプチ雪山を楽しめました。
あらためて万字ズリ山の魅力は凄いなと感じています。
その様子をyoutubeに投稿してみましたので、お時間あれば御覧ください。
この「ズリ山」とは、地下から石炭を採掘する際に、製品となる石炭の他に岩石や低品質の石炭もどきみたいなのが混ざります。通常は坑内の埋戻し等に活用したりもするのですが、それでは足りずトロッコなどで山状に積み上げたものです。
※ズリ山・ボタ山(Wikipedia参照)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%BF%E5%B1%B1
まさに人間が産業の営みの中でつくった人工の山なのですが、これが結構なスケール。
空知管内にはまだまだ各所にズリ山が残っているのですが、階段等がしっかり整備され、誰でも足を運ぶことが出来るのが赤平市ズリ山展望広場と岩見沢市万字炭山森林公園の2箇所であり、他に民間サイドで整備活用されているのが夕張市の清水沢ズリ山。これら以外は許可なく立ち入るのは難しいと認識しています。
そして今、炭鉄港の日本遺産登録の波の中で、各地の炭鉱関連遺産が見直されている状況下、岩見沢の万字炭山森林公園ズリ山がとても高い評価を受けはじめていると感じています。まさにこれからズリ山ブームが来るのではないかと期待してしまうほど。
おそらく岩見沢市民の方々でも、このズリ山の存在を知らないか、知っていても見たこともないというのが一般的かと思います。雪が融けたら、ぜひ森林浴に足を運んでみてはいかがでしょうか(熊よけの鈴などは必要かもしれません。また食べ物を残してくるなどの危険な行為はお控えください!)。
興味はあるけどなかなか行けない!という方がいらっしゃれば連絡ください。
是非一緒に登りましょう♪