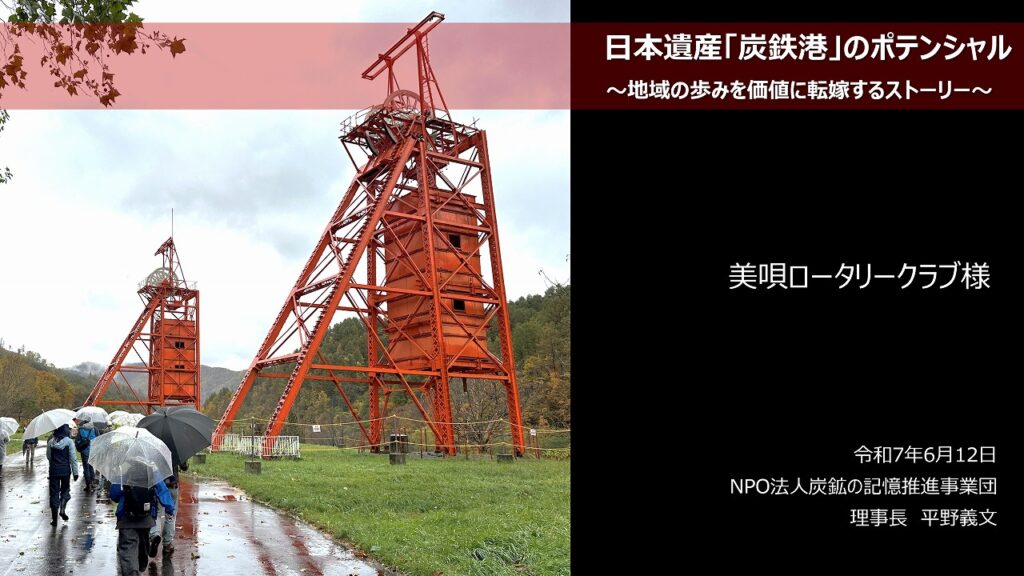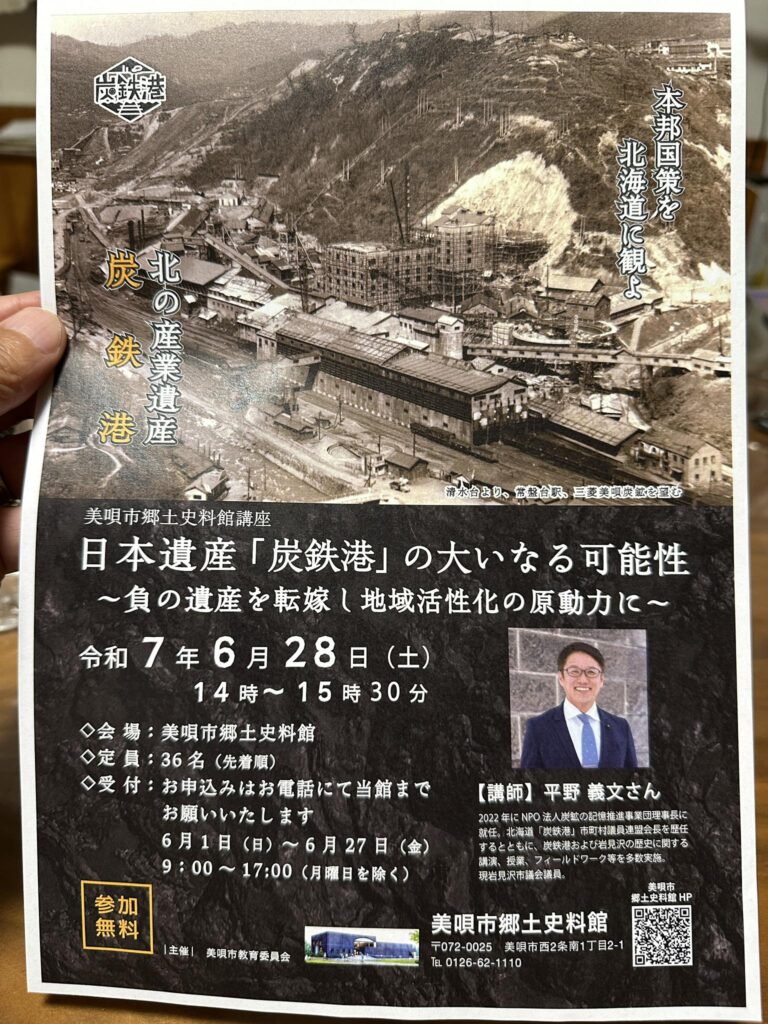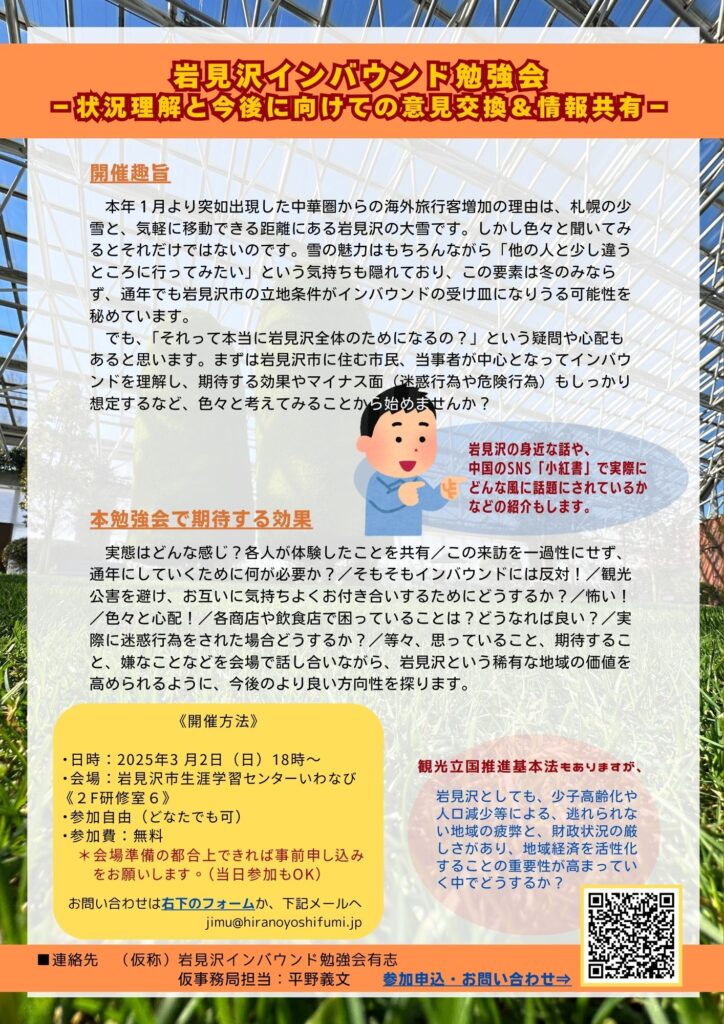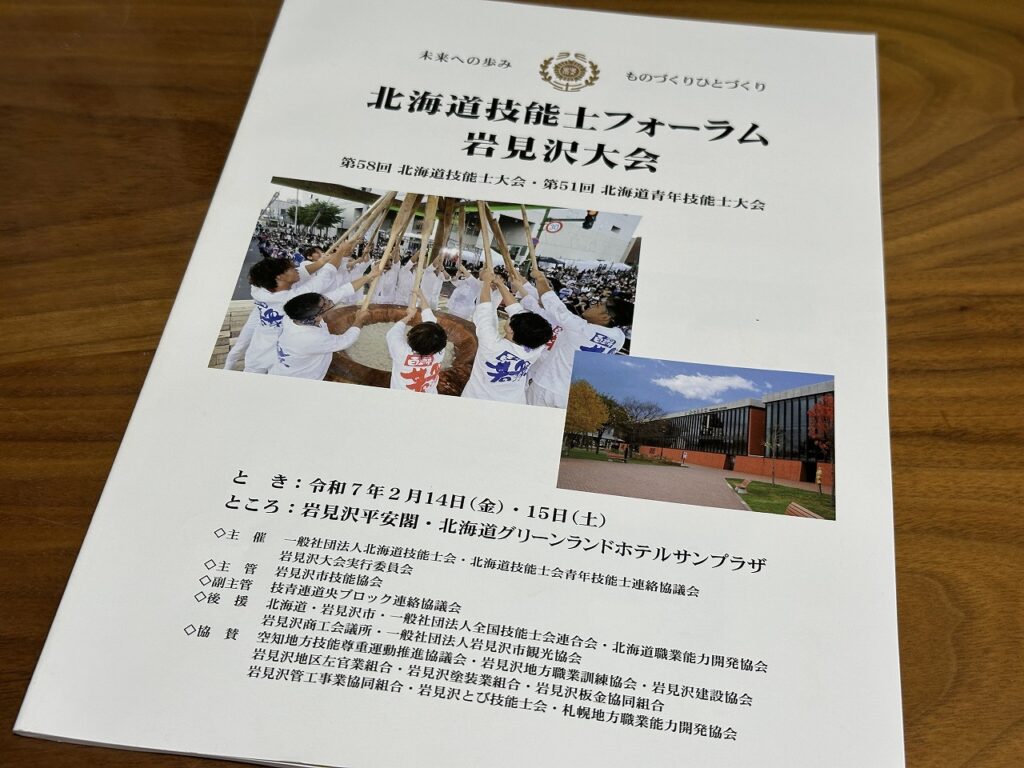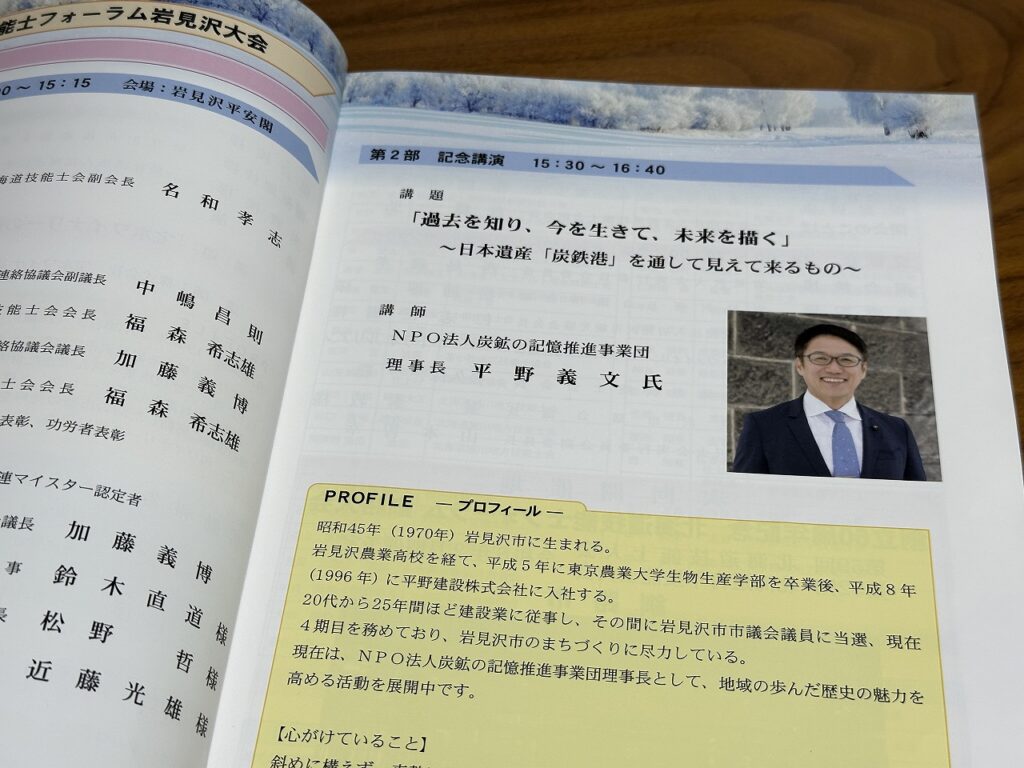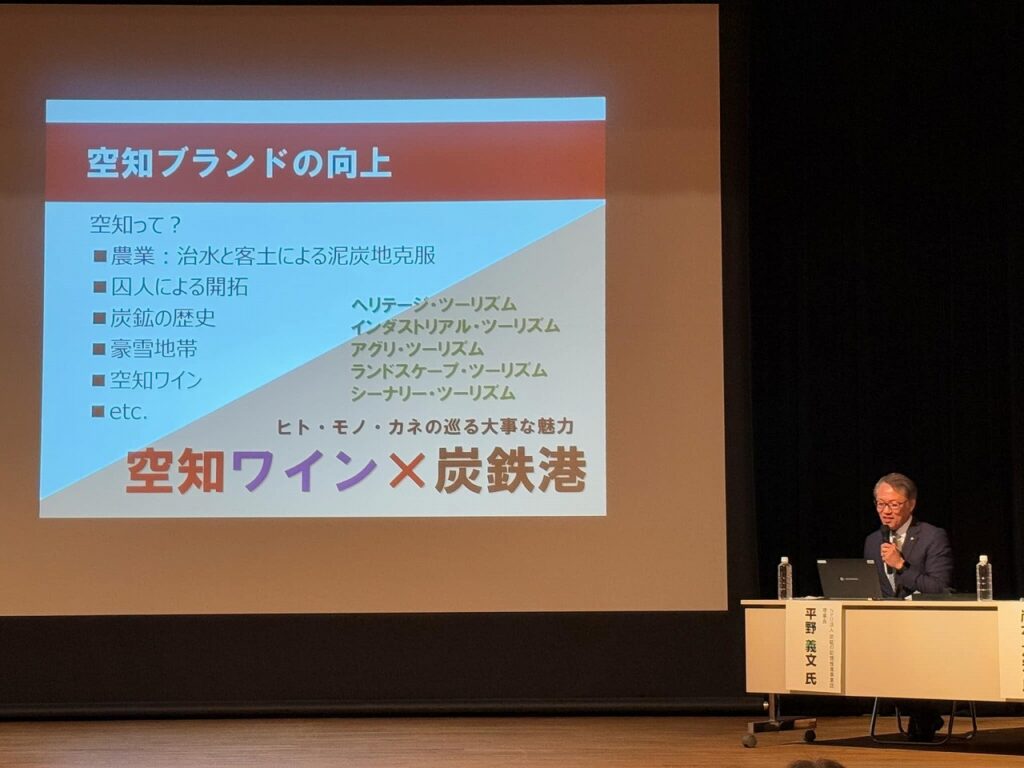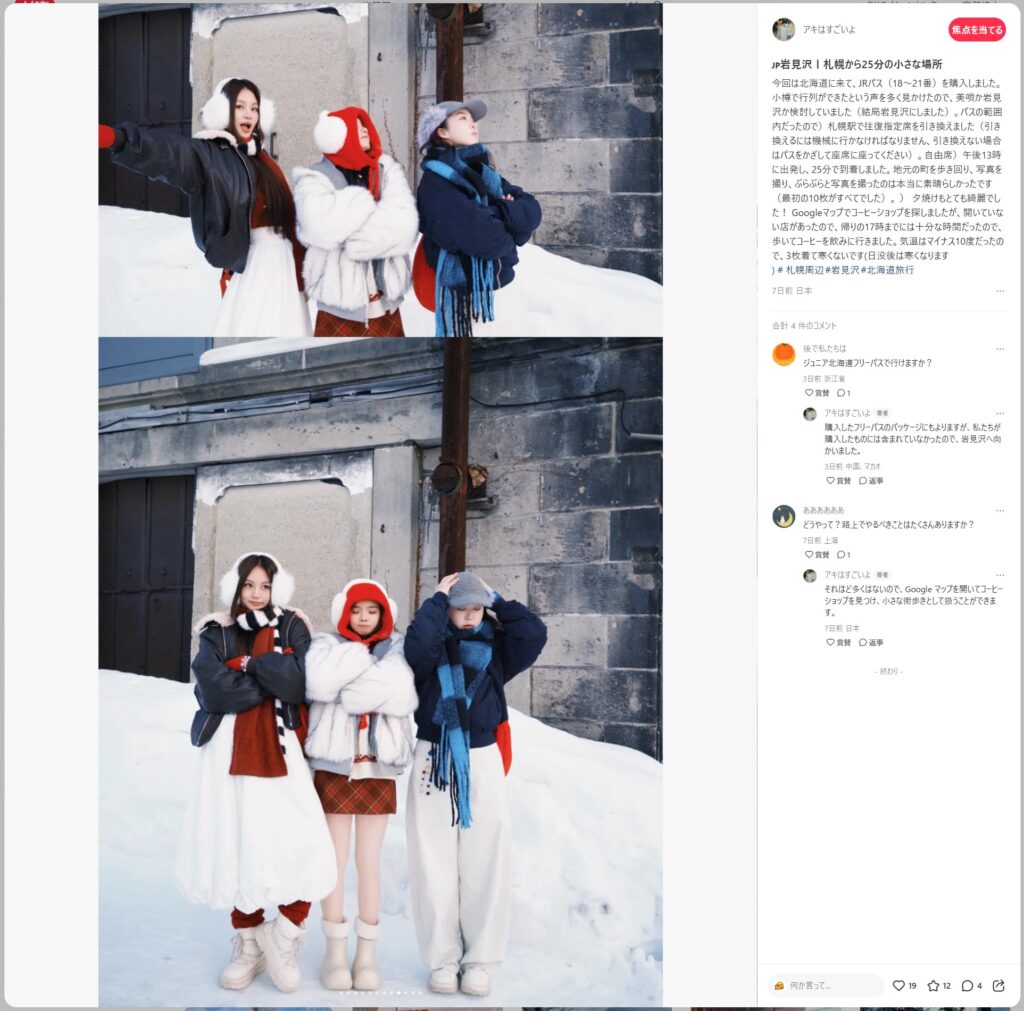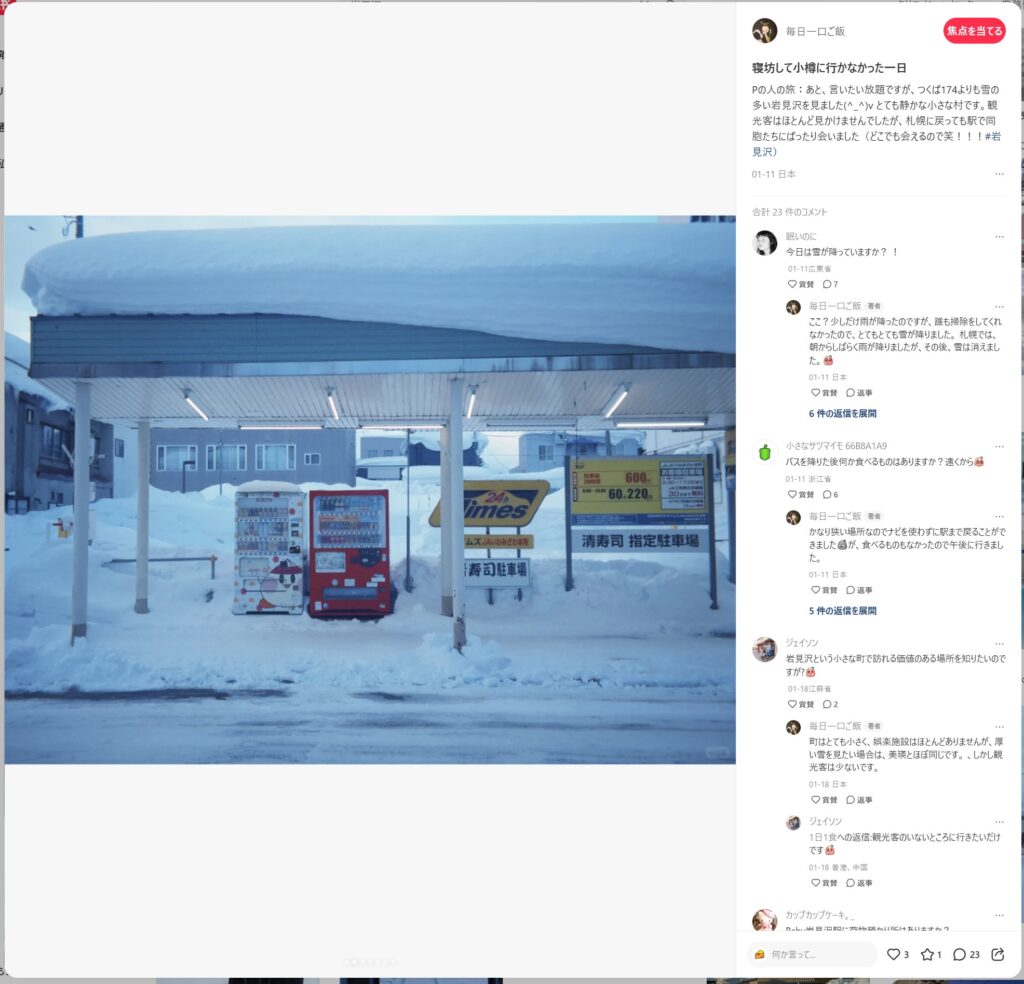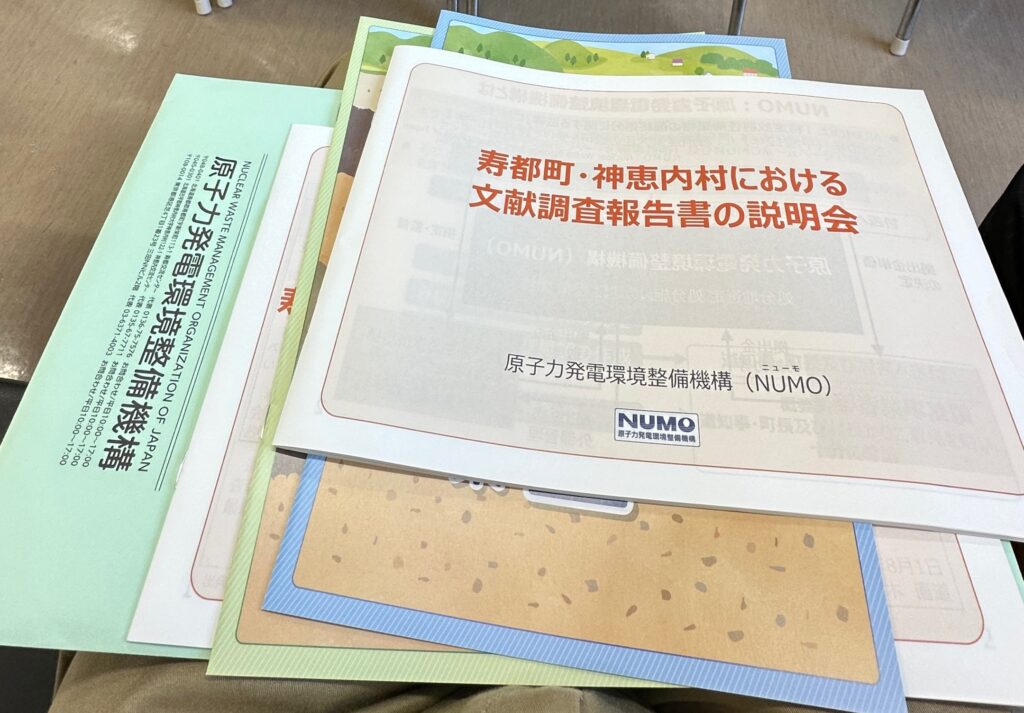〈令和7年1月18日投稿〉
先ほど、岩見沢広域総合福祉センターで開催された表記説明会に参加してきました。時間は14時からスタートし、予定の16時30分を超えて17時近くまでの開催となりました。
このテーマは非常に重たいものがあり、原子力発電所の存在自体が果たしてどうなのか?という結論に至っていない私としては、自身の勉強のためにまずはニュートラルな気持ちで参加してみようと向かった次第です。
( ↓ 2年前の3月11日に投稿した原発に関する投稿)
空知総合振興局管内は今回のみということもあり、市外からも100人を超える方々が集まり満席の状況でした(会場内は撮影不可)。
今回の説明会の主旨は、原発で使用した高レベル放射性廃棄物を「地層処分」するための場所の選定に関し、寿都町と神恵内村からの申し出を元に「文献調査」した結果を全道各地で説明しているものとなります。
説明資料は100ページ近い内容ですが、担当の方の明確な説明により的確に進行します(資料、プレゼン、質疑応答の丁寧な回答を含め、かなり明確で質の高い説明会と感じました)。
内容を掻い摘んで紹介すると、、
■日本の場合は使用済み核燃料を再処理することで95%を再利用できるが、残りの5%が廃液となる。
■この廃液をガラスに溶かして固めたものを地層処分(地下深くの安定した岩盤に閉じ込めて隔離)する必要がある。
■以前は深い海溝等を利用した海洋投棄や、宇宙処分なども検討されたことがあるが、1972年のロンドン条約により各国が自国の中で処分するルールが出来た。
■これまでのように地上で保管しつづけることもできるが、気の遠くなる10万年という長い歳月の中で人為・自然災害リスクも大きい。(ガラス固化体の放射線は、製造後半減期を経て1000年で99%低減するが、10万年単位の管理が必要。)
■1966年の原発稼働以来、既に国内にある使用済み核燃料をガラス固化体に換算すると、なんと27,000本分が存在する。
■ガラス固化体は、1本当たり高さ約1.3m、直径40cm、重さ約500Kgになる。
■このガラス固化体を4万本貯蔵できる施設を、地下300m以上の深いところに設置する必要がある。
■その規模は、地上部分は約1~2平方キロメートル(地方空港ぐらい)で、地下施設は6~10平方キロメートル(新千歳空港くらい)と膨大。
■この施設の設置は、その地域に最新鋭の科学施設ができることとも言える。
■地下300m以上の深い岩盤中に千歳空港(滑走路等含む)の敷地並の大きさでメッシュの様に坑道を掘って保管する
■今回の文献調査の説明は、寿都町、神恵内村共に慎重な各種文献を元にした調査結果で、問題ないと判断できるところと、次の概要調査(現地調査等を含む)をしてみないと判断できない部分などが整理されていた。
■補足:私自身が疑問に思い、質問(ペーパー回収)でコストについて聞いてみたところ、現在の想定は4兆円とのこと(地下300m以深に新千歳空港なみの範囲の面積に坑道を整備し、放射性廃棄物を管理し続けるのに、えっ?そんなので足りる?という印象を持ちました。これら費用も電気代に上乗せされ国民が負担する。)。
ざっくりと言うと、こんな感じになります。
前述2年前の拙稿にも記載していますが、原発の存在が良いのか悪いのかは、今の私には明確な判断がつきません。もちろん、なくて良いなら一つもいらないというのが本音ですが、かつての様に国際情勢が悪化した場合、エネルギー安全保障という面で日本はあまりにも脆弱です。かといってこの狭い国土に50基以上の原発があることも不自然であり、先日の報道にもあったように、ロシアが日本と韓国の原発等を攻撃リストとして作成している。という、当たり前の安全も心もとない状況です。
ましてや既存の古い原発を廃炉にするためにかかる時間と経費や、福島第一原発のように、事故をおこした場合の莫大な費用を考えると、原子力発電所は電気代が安くなるというのは都市伝説であると感じています。
ただ、本当に日本に石油やガス、石炭が輸入できなくなった場合、この国はどうなるのか?というエネルギー問題は想定しておかなければならないのだろうと思います(まぁ、そんな事態になれば残念ながら食料自給率の方が深刻かもしれませんが)。現在、約20%のシェアを占める自然エネルギーにしても、太陽や風力はその出力が自然に左右されるため安定性が欠けます。大きく思想を後退させ、カーボンニュートラルを無視して石炭火力に頼るとして、現在でも国民1人当たり年間約1tもの石炭を輸入をしている状況下、まだ道内の石狩炭田だけでも数十億トンの石炭埋蔵量があるにしても、働き手が不足する労働供給制約社会において、地下1000m以上もの酷所から現行の労働基準法で採炭することができるのかどうか?これまた非常に懐疑的であるのも事実です。
これからDX等も更に進み、ますますICT産業が伸びていけば、データセンターや生成IA等を含め、より多くの電力が必要とされていきます。
その時にゼロカーボンの推進が不可欠とされる環境下、日本は原発がなくてクリアできるのか?
だとしたら、そこで発生する核のゴミはどうするべきなのか?
いくら考えても明確な答えは出ませんが、現代社会はパンドラの箱を目一杯開けてしまっている状況なのかもしれません。
ちなみに、、寿都町や神恵内村の文献調査手続きがニュースになった当時、現地の方の「人口減少も酷いし、今後も地域を残すために仕事と交付金が欲しい」的なインタビューを見た記憶がありますが、この思考はあまりにも「イマダケカネダケジブンダケ」という印象を受けました。
もちろんそんな思考ではなく、「もう先送りすべきでない課題を、この世代で解決すべき」という思考は必要だと思います。
だからこそ、候補地選定には日本全体を俯瞰した視点と十二分な配慮が必要なのだろうと思うのです。
なお、北海道には「(前略)私たちは、健康で文化的な生活を営むため、現在と将来の世代が共有する限りある環境を、将来に引き継ぐ責務を有しており、こうした状況の下では、特定放射性廃棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いことを宣言する 。」 という《北海道における特定放射性廃棄物に関する条例(平成12年10月24日公布)》という条例が存在しており 、現状ではいくら寿都町や神恵内村が適地とされたとしても、この条例が優先されると思われます。
しかし、もし道内で「適地」とされる場所が出てきた場合、私たちはこの条例の改正を含め、どういう判断をしたら良いのか、、やはり考え続けていかなくてはならないと思っています。
さて、皆さんはどう考えるでしょうか・・・
【参考】
○地層処分についてはこちらをどうぞhttps://www.numo.or.jp/chisoushobun/ichikarashiritai/
○産経ニュースの企画広告https://www.sankei.com/special/numo2016/article-1.html
○ガリレオchもどうぞ!
VIDEO